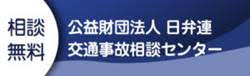奈良弁護士会
会長 兒玉 修一
会長 兒玉 修一
- 本年6月に成立した改正公職選挙法では、選挙権付与年齢を満18歳に引き下げるとともに、その附則において、「少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」とされた。そして、これを受けて、自由民主党は、「成年年齢に関する特命委員会」を設置し、選挙権付与年齢にあわせて少年法の適用年齢もあわせて引き下げる方向での検討を始めており、今国会会期中には結論が示される見込みである。
しかし、以下のとおり、少年法の適用年齢の引き下げには反対である。 - そもそも、選挙権付与年齢の引き下げは、若者の意見を国政に反映させると同時に、若者にも国政に関心を持ってもらい、民主主義をこれまで以上に機能させようとしたものである。他方、少年法の趣旨は、心身の発達が未熟で可塑性に富む未成年者に対しては、刑罰を科するのではなく保護処分によって教化をはかるべきという「保護主義」にあり、両者の趣旨は全く異なる。また、歴史的にみても、選挙権付与年齢と少年法の適用年齢は、常に一致していたわけでもない。したがって、両者の年齢を一致させなければならない必然性は乏しい。
- ところで、昨今、少年が犯した一部の残虐な事件が大きく報道され、少年に対する処分は軽すぎる、重大な罪を犯した少年は、大人と同様に厳しく処罰すべきだ、といった意見が見受けられる。また、殺人、強盗、放火、強姦事件(以下「重大事件」という)等の増加を念頭に少年法の適用年齢を引き下げるべきとする議論もある。
しかし、いずれも説得力のあるものではない。現行の少年法においても、少年による一定の重大事件等については、検察官送致(逆送)により、成人と同様の刑事裁判を受ける可能性がある。そして、少年が刑事裁判を受けた場合の刑罰については、2014(平成26)年6月に、厳罰化する方向での改正が行われたばかりであるから、少年に対する処分が軽すぎるとは一概に言えない。また、最高裁判所の調べによれば、2013(平成25)年の少年保護事件の新受人員数は、2004(平成16)年に比べて47.8%も減少しており(この間の少年人口の減少率は9.7%にとどまる。)、少年犯罪は近年急減している。少年による重大事件についても増加しているとの事実はなく、2013(平成25)年における少年保護事件新受人員数全体のわずか0.6パーセントにすぎないことからも明らかである。 - もっとも重要なのは、少年法の適用年齢の如何を議論するにあたっては、少年保護事件全体に及ぼす影響について慎重に考慮されなければならないことである。
この点、少年法の下では、少年は成人の場合と異なり、犯罪の嫌疑があれば全件が家庭裁判所に送致され(少年法第41条)、少年鑑別所や家庭裁判所調査官によって、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識を駆使して、少年自身や保護者、関係人の行状、経歴等の環境についてまで詳細に調査される(少年法第8条)。そして、これらすべての調査結果に基づいて、家庭裁判所は少年を健全に育成し少年の再非行を防ぐために最も適切な処分を下してきた。
仮に、少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げると、18歳、19歳の少年が、これまでと異なり、成人の刑事手続で処分されることになる。その結果、少年鑑別所や家庭裁判所等による上記のような事件の背景事情等の調査が十分に行われないまま少年が処分されることとなり、かえって少年の更生の機会を奪い、少年の再犯リスクを高めてしまう危険性すら存在する。 - 以上のとおり、少年法の適用年齢を引き下げるべき合理的な理由はなく、むしろ弊害が多い。したがって、当会は、これに強く反対する。
 奈良弁護士会
奈良弁護士会