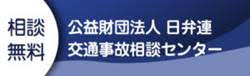奈良弁護士会
会長 佐々木 育子
会長 佐々木 育子
- 2016年3月1日、最高裁は、愛知県大府市内で認知症の男性が徘徊中に駅のホームから線路内に進入し、列車と衝突した事故につき、東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」という)が男性の妻と長男に損害賠償を求めた裁判において、JR東海側の請求を全面的に棄却し、男性の妻と長男は、民法714条の法定監督義務者には当たらず、これに準じる者ともいえないとして、損害賠償責任を否定する判断を下した。
- その理由として、最高裁は、1999年に、精神障がい者の保護者に対する自傷他害防止監督義務(旧精神保健福祉法22条1項)が廃止されたこと(なお保護者制度そのものも2013年に廃止)、後見人の禁治産者に対する療養看護義務(民法858条1項)も、身上配慮義務に改められ、後見人に事実行為として現実の介護を行うことや被後見人の行動を監視することを求めるものではなくなったことをあげ、本件事故当時には、保護者や成年後見人であるからといって直ちに法定の監督義務者に該当するということはできないと判示した。また、民法752条の夫婦の同居、協力、扶助の義務も、第三者との関係で夫婦の一方に何らかの作為義務を課すものではなく、精神障がい者と同居する配偶者であるからといって、同条を根拠として民法714条1項にいう法定の監督義務者にあたるということはできないと判示した。
- このような最高裁の結論は、急速に進む超高齢社会の中で、認知症高齢者が増え続け、2025年には700万人に達すると推計されていることや、核家族化が進行し、介護が必要な高齢者がいる世帯のうち、介護をする人も65歳以上である「老老介護」世帯の割合が過去最高の51.2%を超え、もはや家族だけで介護を支えるのは限界であるということ、成年後見制度も、親族でない第三者が成年後見人等を務める割合が70%に達し、認知症高齢者を実際に監督する義務まで負わせるのは困難であること等の社会の変化を考えると、現実をふまえた妥当なものと評価できる。
- しかし最高裁が、法定の監督義務者に該当しない者であっても、その者が精神障がい者を現に監督しているか、あるいは監督することが可能かつ容易であるなどの事情があれば、衡平の見地から、準監督義務者として、民法714条1項を類推して損害賠償責任を問うことができると判示したことについては、その責任の範囲について慎重に判断されるべきであると考える。木内裁判官の補足意見にもあるように、他害防止を含む監督と介護は異なるものであり、介護の引受と監督の引受は区別されるべきである。ノーマライゼーションの理念が浸透し、国の政策としても、認知症高齢者ができるだけ最期まで地域の中で、自分の望む暮らしができるように支援するという地域包括ケアをめざしている中で、介護を引き受けた者に監督責任が問われうるということになれば、在宅での暮らしを支える者がいなくなり、施設や病院への収容を余儀なくされるおそれがある。むしろ、民法714条1項の適用は出来るだけ制限的に考えるべきであり、認知症高齢者の他害行為防止の責任を、特定の人間だけに負わせるのではなく、認知症高齢者に対する地域での見守り強化や、介護保険の十分な活用による福祉関係者の緊密な連携により、社会全体で担っていくべきと考える。また事故が発生した場合に備え、被害者の速やかな被害回復のために、企業の側でも想定される事故については損害保険の加入によりリスクの分散を図るべきであるし、認知症高齢者が自立して生活していくための総合的な損害保険の普及等の個人の被害者の救済の取り組みも必要である。
- 当会は、この最高裁判例を受けて、今後も、誰もが住み慣れた地域の中で、自分の望む暮らしを実現するという地域包括ケアの理念を、法的にサポートし、認知症高齢者やその家族が社会から孤立しないように見守る専門職団体の一つとして、地域の中でなお一層連携の取り組みを進める所存である。
 奈良弁護士会
奈良弁護士会