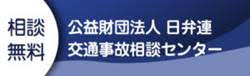2021(令和3)年11月5日
奈良弁護士会
第1 本意見書の趣意
2016(平成28)年10月7日の第59回日弁連人権擁護大会において「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」が採択されて以来、日弁連は死刑制度の廃止へ向けた活動を推進し、他方、死刑制度の存置を主張する日弁連会員からは同宣言に対して強い批判が寄せられ、死刑制度の存廃をめぐって激しい議論が繰り返されている。
しかし、これらの議論においては、ともすると観念的ないし抽象的な存廃の議論が先行しており、法律実務家としての見識に基づいた司法上の刑罰制度の観点から現行の死刑制度の問題点が具体的に論じられることはあまりない。
よって、本意見書は、死刑制度自体の存廃の論議とは別に、まず現行の死刑制度には司法上の刑罰制度としての重大な問題点があるとの立場から、早急に改革が必要な検討課題を明らかにし、その改革の方向を提言するものである。
本意見書は、死刑制度の廃止を提唱するものではない。しかし一方で、死刑制度の存続を所与の前提とするものでもない。現在の死刑制度に存在する司法制度としての根本的な問題点を明確にし共有することが目的であり、将来的な制度自体の廃止あるいは存置についての国民的議論も、かかる問題点を解決することが可能かどうかという観点からこそなされるべきとの問題意識に基づくものである。
第2 死刑事件についての公判手続法の問題点と改革の方向性
1 スーパー・デュー・プロセス法理について
現行法上、死刑事件(死刑求刑事件または死刑の判決がなされる事件)とそれ以外の刑事事件との間で、手続において差異は設けられていない。
しかし、死刑は、被告人の生命を奪うという究極性および不可逆性において、無期懲役刑以下の刑とは、刑罰のあり方において根本的な断絶が存在する。すなわち、死刑と無期懲役刑以下の刑との差異は、程度問題や分量問題の次元の問題ではない。
のみならず、司法制度論的観点からみれば、死刑とは、当該受刑者の存在という最大の立証手段を根本から奪い去る行為であるから、判決や刑罰の正当性を事後的に担保する手段を完全に喪失させるという意味においても、無期懲役刑以下の刑とは根本的な差異が存在するものというべきである。
したがって、死刑事件においては、有罪・無罪の判断はもちろんのこと、量刑冤罪(本来、無期懲役刑以下になるべき事件が死刑となるもの)もまた深刻な誤判であるといえる。
実際、量刑冤罪の問題はわが国の刑事裁判実務でも意識されている。すなわち、裁判員制度は量刑にも市民の意見を反映させることが制度目的の一つであり、裁判員裁判の量刑判断は上級審でも基本的には尊重されるべきとされている。それにもかかわらず、死刑についてはそうではなく、裁判員裁判での死刑判決を破棄して無期懲役とした上級審判決がいくつか存在する。このような上級審の姿勢からは、高裁や最高裁においては、無期懲役と死刑の選択については判断の幅を認めていないことがうかがえる。
この点、量刑判断を含む死刑事件の誤判防止の観点から、近時、アメリカ合衆国においては、憲法上、死刑事件については、それ以外の刑事事件とは異なる、特別に信頼性の高い適正手続の保障が必要であるとの見解(スーパー・デュー・プロセス法理)が広く支持され、量刑冤罪も含めた誤判防止のための制度改革が行われている。
死刑事件の誤判防止はわが国においても共通する重要な課題であり、同様の制度改革が必要であると考える。以下、アメリカ合衆国のスーパー・デュー・プロセス法理の示唆を受けて、特に制度改革が必要な点について意見を述べる。
2 死刑求刑の事前の明示について
わが国の刑事裁判実務においては、そもそも、ある事件について死刑求刑の可能性があるかどうかということ自体が、公判の最終段階における検察官の意見陳述(いわゆる論告および求刑、刑訴法293条1項)まで分からない。
しかし、スーパー・デュー・プロセスとは、刑事訴訟手続の全般にわたって問題となるのであるから、死刑求刑の予定が検察官からあらかじめ明らかにされない限り、そもそも機能しうるものではない。
したがって、スーパー・デュー・プロセスを実施しようとするならば、①遅くとも公判前整理手続において死刑求刑の予定が検察官によって明らかにされること、 ②検察官がこれを明示しなかった事件については、裁判所はこれに拘束され、死刑判決をなすことができないことという法制度の確立が必要となる。
3 審理手続二分制度の導入について
現行刑事訴訟制度上、事実認定に関する手続と量刑判断に関する手続は、同一の手続内において一体として行われているところである。
しかしながら、死刑が恣意的に決められることを可及的に排除するためには、後述のとおり量刑資料についても徹底した審査が行われなければならない。そのためには、現行制度のような、特に無罪を主張する場合に「無罪を主張しつつ量刑事情についても主張する」という枠組では、構造的に主張立証の不十分(特に量刑事情について)をきたす危険性は高いものといえる。
したがって、特に死刑事件について量刑冤罪を防止するためには、事実認定に関する手続と量刑判断に関する手続を明確に区別する審理手続二分制度が導入されるべきである。この制度を前提としてこそ、次項に述べる量刑判断資料の充実化がはじめて可能となるのである。
4 量刑判断資料の充実化について
死刑事件においては、死刑以外の選択肢がないのかという点について、あらゆる角度からの徹底した検証がなされる必要がある。
アメリカ合衆国において、1976年のウッドソン判決が、死刑事件においては「個々の犯罪者の性格および経歴、そして当該犯罪の事情を考慮すること」が修正8条(わが国の憲法36条の母法である。)の理念が要求するところであると述べ、その後の判例の展開によって、これらの事情に関しては、被告人側から提出される刑の減軽証拠については、それを考慮すること自体は拒絶してはならないとされている。その効果として、死刑事件においては、被告人の成育歴や生活歴に遡ってまでのあらゆる証拠が裁判所に顕出されるのが通例である。
これに対し、わが国の裁判員裁判においては、「裁判員の負担軽減」を口実として、「証拠の厳選」や「事前に策定した審理計画の遵守」という理由により、量刑資料についても、証拠からの排除ないし証拠調の不実施が少なからずみられる。 しかしながら、死刑が極めて重大な判断である以上、死刑を回避すべき事実の不存在については、徹底した検証が審理段階でなされなければならないのであり、死刑事件においては、被告人側から提出される減軽証拠は原則としてすべて採用決定がなされなければならない。とりわけ、いわゆる情状鑑定については、すべての死刑事件において実施がなされるべきである。
5 特別な評決制度の創設について
死刑事件は、原則として裁判員裁判で評決がなされることになるが、評決要件について死刑事件について特別な要件は設けられていない(裁判員法67条1項)。
しかし、死刑については、生命を奪うという究極性および不可逆性という刑罰の特殊性から、それ以外の事件とは異なる、より厳格な評決要件とすることが必要である。
また、わが国固有の事情として、刑法典において死刑を科すべき場合について、明確な規定が設けられていない。最高裁は、死刑の判断基準として、いわゆる永山基準に依拠しているが、これは死刑判決を下す際に考慮すべき観点を並べたものであり、明確な死刑判決の要件を提示するものではない。実際、最高裁においても、永山基準に依拠しながら、死刑か否かで裁判官の意見が2対3に分かれた事案がある。しかし、上記のとおり死刑判断について明確な規定がない中で、判断が難しい事案の審理において裁判体の中で意見が分かれている場合に他の事件と同じ評決要件で死刑という判断が下されることは、裁判体の人的構成という偶然的事情で結論が異なることにならないかとの疑問がありうる。
以上の理由により、わが国においても、裁判員法を改正し、死刑判決には他の事件とは異なる特別な評決要件を定めて死刑事件の量刑を含めた誤判の可能性をなくすことが目指されるべきである。
6 自動上訴制度の導入について
自動上訴制度とは、死刑判決がなされた場合、当該被告人の意思いかんを問わず自動的に上級審に審理が移行し、改めてその是非が審理されるというものであり、アメリカ合衆国の死刑存置州の多くで州法において設けられている。
これに対し、わが国においては、死刑判決に対する自動上訴制度がなく、したがって、弁護人が行った上訴手続を被告人自身が取り下げてしまうといったこともしばしば起こり、その取下行為の有効性が争われることもある。
しかし、スーパー・デュー・プロセス法理の下では、死刑判決が疑いのないものであることについてはあらゆる角度から検証がなされなければならないのであるから、これを貫徹するならば、被告人のその場の主観的意思のみによって確定裁判の結果が左右されるのではなく、多角的かつ重層的な検証を行うため、死刑判決に対する自動上訴制度を導入すべきである。
なお、わが国の現行法においても、死刑および無期懲役・禁錮刑の判決に対する「上訴の放棄」は認められていない(刑訴法360条の2)。すなわち、一定の重大な刑罰については、手続上、当事者の意思と無関係に上級審の判断を受けられるようにするという態度は、すでに現行法にも表れているのであって、自動上訴制度は現行法とも連続性のある制度改革である。
7 弁護活動の充実について
以上の法理を実際の事件について具体化および現実化するためには、あらゆる事件について弁護活動を充実させる制度的担保が必要となることは当然である。
この点につき、アメリカ法律家協会が定めた死刑事件弁護に関するガイドラインにおいては、死刑事件弁護では、2名以上の死刑事件を扱う資格のある弁護士、調査員および減軽証拠の専門家によって構成されるチームによる弁護が行われるべきであるとされている。のみならず、弁護人の徹底調査義務違反はそれ自体が死刑判決の破棄事由となるとされており、チームは、被告人に関するあらゆる減軽事由の有無について徹底的に調査し、その証拠を収集しなければならない。そしてその活動は、基本的には裁判所からの費用支払によって確保されている。
以上に比べると、わが国の死刑事件に関する弁護支援体制はあまりに貧弱であり、担当弁護人の善意に基づく手弁当に頼ってしまっているところが大きい。この点、抜本的改革が急務である。
8 小括
このように、スーパー・デュー・プロセス法理に照らした場合、わが国における現在の死刑事件手続のあり方には大いに問題があり、真に「やむをえない場合の刑罰」として死刑が行われているかということには多大な疑問がある。
死刑制度そのものの存廃の議論をひとまず措いたとしても、死刑のような究極的かつ不可逆的な刑罰を科すために特別に信頼性の高い手続になっているかどうかという点については、現行制度は多くの点において欠陥を抱えており、抜本的改革が必要となるものと考えられる。改革がなされなければ、現行制度は憲法31条、3
6条に違反する疑いが生じると思われる。
第3 死刑執行方法の根拠法の不存在
1 死刑執行方法に関する現行法の規定
現行法上、死刑の執行方法については、刑法11条において、「刑事施設内において、絞首して」執行すると定められている。さらに、刑事収容処遇法178条1項は、刑事施設内の「刑場において」執行すると定め、同法179条は、執行の際には「絞首された者の死亡を確認してから五分を経過した後に絞縄を解くものとする。」と定めている(その他、刑事訴訟法475条以下には、執行命令や立会人等の規定がある。)。
2 具体的執行方法の法的根拠の欠落
しかしながら、上記の点を除き、現行法下において、死刑執行の具体的方法は何ら定められていない。例えば、執行のための設備や器具、手順等に関してもまったく定められていない。現在、それらの点に関する根拠とされているのは、明治6年太政官第65号布告における「絞罪器械図式」である。すなわち、一国の刑罰の最重刑の執行方法が、国会での立法によらない明治6年太政官布告に基づいてなされているのである(しかも、現在の執行においては、そもそもこの布告に対してすらもいくつもの点で従っていないことが指摘されている。)。
3 現行法上の問題点
このように、死刑の執行方法に関しては、法律に定める手続がほとんど存在しないことから、以下のような議論が考えられるところである。
(1) 刑法11条に定める「絞首」とは何か。また、この執行方法は、執行方法として適正かつ合理的なものといえるのか。その根拠は存在するか。
(2) 「絞首」という以外に具体的な手法が何ら法律上定められていない現行法は、適正かつ合理的なものといえるのか。そもそも、一国の刑罰法規における最重刑の執行方法を定めた法律が存在しないことが、今日における国家のあり方として許容されるのか。
4 検討
これらの点については、死刑制度の存廃をめぐる国民の間の論議においても、ほとんど意識されていないように思われる。そもそも、上記のように死刑の執行について法律上の手続規定が欠落しているという点自体、国民の間で知識として共有されているとはいえない。
なお、この点について、最高裁大法廷昭和36年7月19日付判決においては、「死刑の執行方法の基本的事項は法律によって定められるべき事項であるが、太政官布告第65号は旧憲法下においても法律としての効力を有しており、現憲法下においても法律と同一の効力を有する」旨を述べているところである。しかし、この理論構成自体にそもそも疑義があるのみならず、国民の間における議論としては、明治6年当時の死刑に関する社会的認識をそのまま現時点においても維持できるものであるかそれ自体が問われなければならない。
そもそも、死刑制度の存廃そのものについてはもちろん、執行方法についても、その時代と環境に応じて結論が変わりうることについては、すでに最高裁大法廷昭和23年3月12日付判決での多数意見および補足意見においても述べられているとおりである。すなわち、現行の執行の手法を無批判に今後も継続していくことは、到底許されないのである。
5 改革の方向性
執行方法の規定の欠落に関する意識の共有と、それを基盤とする執行方法に関する議論を普及させていくことは、以下のとおり死刑の存廃問題への理解を深めるためにも必要である。この意味からも、死刑制度の存廃をめぐる国民の議論を活性化させるためには、執行方法の規定の欠落に関する意識の共有と、それを基盤とする執行方法に関する議論を普及させていくことが必要であると考える。
そしてその際には、以下の点に留意する必要がある。
(1) 死刑存置論の立場においては、上記のような規定の欠落の状態を意識した上で、「あるべき死刑の具体的執行方法」を積極的に提唱すべきである。制度としては死刑を存置すべきであるが、その執行方法については考えていないというのであれば、国家の最高刑罰法規を考えるあり方として、責任ある意見とはいえないからである。
(2) 死刑廃止論の立場においては、そもそも制度自体に反対なのであるから、執行方法を論ずる必要などはない、という考えに流れがちである。しかし、「執行方法が法律上存在しない」という点自体は、存置論でも廃止論でも共通に問題意識を持つことができる論点であり、廃止論の立場からすれば、「適正かつ合理的な執行方法は存在しない」という論証を行っていくことは、存置論に対する有効な議論拡大の方法であるという点を意識する必要がある。
(3) 以上のとおりで、死刑の執行方法を定めた法律がないという問題点は、上記のとおり、存置論者にとっても廃止論者にとっても、放置することが許されない問題というべきである。また、この問題点は、共通の基盤で議論できる明確な論点を含み、国民の間で議論を形成していくことが可能であるという特徴がある。 こうした議論を通じて、死刑という制度について抽象的な是非論の次元ではなく、具体的な執行手法を伴った司法制度としての死刑制度の理解が深まることが期待される。このようないわば現場感覚があってこそ、存置論の立場からも廃止論の立場からも、内実を伴った国民的議論の喚起が可能になると考えられるからである。
第4 死刑囚の処遇の問題点と改革の方向性
1 死刑囚の処遇についての法的規律
死刑囚の処遇の基本原則は、刑事収容処遇法において規定されており、同法第32条1項によれば、死刑囚が心情の安定を得られるようにすることに留意するとされている。
その上で、同法第36条において具体的な処遇の態様が規定されている。それによれば、原則的に昼夜居室で処遇すること(1項)、単独室(独房)で処遇すること(2項)、原則的に居室外においても相互に接触させてはならないこと(3項)が規定されている。
さらに、各拘置所における死刑囚の具体的処遇については、各拘置所が定めた死刑確定者処遇規程によって定められている。
ここで念頭に置かれるべきことは、死刑囚の拘束は、あくまでも死刑執行を確実に行うための身柄の拘束であって、それ自体が刑罰ではないということである。
その観点からすると、わが国の死刑囚の処遇には以下のとおりの問題点が存在しており、早急な改革が必要である。
2 問題点の検討
(1) 死刑の執行の告知が執行直前になされること
死刑確定者本人に対する執行の告知は、執行当日、しかも、執行の約1時間前に行われる。このような運用は1976年頃から始まったとされ、多くの場合、執行日の朝に告知される。死刑確定者たちは、毎朝、執行の恐怖に晒されていて、その恐怖は耐えがたいものとされている。
また、家族や関係者に対しても事前通知が一切なく、最後の別れをする機会がない。これについては、人道的見地から問題であるし、国連人権(自由権)規約委員会からも、人権規約と相容れない処遇であるとして批判されている。
また、弁護人に対しても事前告知がなされないために、再審、執行停止あるいは恩赦の申立など、必要な弁護活動をする機会が奪われる可能性がある。
この点、世界的にみて数多くの死刑が執行されている中華人民共和国においても、執行は数日前に告げられ、死刑囚は執行前に家族や友人と会う機会が与えられ、記念撮影をすることすら許されており、それと比較しても、わが国の死刑囚に対する扱いは、極めて非人道的なものといわざるをえない。
(2) 日常生活に関する処遇について
前述したように、死刑囚の処遇の基本原則は「心情の安定」とされているが、実際には、収容の維持管理が最重要視されている。東京拘置所の規程においても、死刑囚に対する「動静視察並びに身体、着衣、所持品及び居室の検査は、頻繁かつ綿密に行い、逃走、自殺等の事故防止に努めること」と規定されている(3条2項)。現実には、逃走や自殺防止という形式的理由の下に、死刑囚は過酷な扱いを受けている。
すなわち、死刑囚監房収容者は、許可なく立ったり、横になったり、動いたりすることは許されず、基本的には机の前で座っていることを求められ、刑務官の頻繁な巡回により監視されている。
さらに、多くの拘置所では、就寝中も照明が消されることはなく、運動、入浴の回数や時間が厳しく制限されている。書籍・新聞・パンフレットなどについては、閲読自体は許されているが、冊数などが制限される上、検閲・抹消がなされる。ラジオは、希望する番組を自由に聴くことができない拘置所が多く、テレビについては原則録画されたものしか見ることができず、その視聴回数も月1回~2回であり、しかも1回あたり1時間半~2時間程度と厳しく制限されている。
すでに述べたとおり、死刑囚の拘束とは執行を確保するためのものであって、それ自体は刑罰ではないことを考慮すると、このような過酷ともいえる自由の制限は憲法の人権規定に違反している疑いが極めて強く、少なくとも国際的な人権保障の水準を大幅に下回っていることは明らかである。
(3) 過度な面会の制限
1963(昭和38)年の矯正局長通達により、死刑確定者は、「一般社会とは厳に隔離されるべきものであり、拘置所等における身柄の確保及び社会不安の防止等の見地からする交通の制約は、その当然の義務であるとしなければならない」とされ、死刑囚の外部交通は厳しく制限されるようになった。
現在、外部交通が許されるのは、本人の親族(内縁の妻を含む。)、本人の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のために面会することが必要な者、面会により本人の心情の安定に資すると認められる者に限られる。
しかし、実際の運用では、親族や弁護人以外の者との面会が許される場合は極めて限定され、いわゆる友人・知人との交通が認められることはまずない。この点、連合国軍による占領期においてすら、死刑囚が友人・知人とかなり自由に交通できたのとは対照的である。
3 小括
以上のとおり、現在の死刑囚に対する処遇は、執行を確保するための身柄の拘束という目的を超えた過度な自由の制限であるものといわざるをえず、早急に改革がなされるべきである。
第5 死刑制度の情報非公開の問題
1 日本の死刑制度の運用についての情報の閉鎖性
まず、わが国においては、死刑執行の決定プロセス自体がすべて非公開である。すなわち、110名の死刑囚(2020(令和2)年末時点)の中からいかなる基準や根拠によって執行対象者が選ばれるのかという過程は、まったく明らかにされていない。少なくない死刑囚が、数十年にわたって勾留され続けた挙げ句に執行を待たずに病死する一方で、確定から比較的短い時期に執行される死刑囚も存在するが、その理由も一切明らかにされていない。
さらに、その執行には、報道関係者はもちろん、死刑囚の関係者や事件関係者が立ち会うこともできない。加えて、執行された状況については詳細な報告書が作成されるが、その内容は大半が非公開であり、研究者や報道関係者であっても、当該公文書へのアクセスが拒否されている。
したがって、わが国においては、死刑執行のプロセスそのものが国民に対して隠蔽されているのみならず、その事後的な検証すらも不可能となっているのである。 これに対し、アメリカ合衆国においては、死刑存置州のほとんどにおいて、執行予定日が1か月以上前に決定され、本人に通知される。さらに、その情報が速やかに公開されるので、誰でもインターネットで確認できる。また、死刑囚の関係者、事件関係者および報道関係者はもちろん、申請した州民なら誰でも立会を認める州も存在する。
2 検討
わが国とアメリカ合衆国とでは文化や風土が異なっており、アメリカ合衆国式の情報公開をただちにわが国に導入すべきかという点については、様々な意見がありうるものと思われる。
しかし、アメリカ合衆国が死刑に関して情報公開に努めている理由の一つは、「死刑は国家による殺人である重大な行為」であるから、「国家が重大な決定を下すときには、国民はそれを監視する必要がある」という考え方にある。この考え方自体は、基本的人権の尊重と国民主権を原理とするわが国においても、基本的に妥当するものである。
すなわち、生命を奪う刑罰という死刑の重大性ゆえに、死刑制度の運用については、国民による不断の監視と検討が必要である。その上で、正確な情報に基づく実のある国民的論議が必要なのであり、そのためには、死刑執行の実態についての大幅な情報公開が必要不可欠である。
逆にいえば、現在の死刑制度の運用に関する情報公開はあまりにも秘密主義ないし閉鎖主義であって、そもそも国民が論議を行う前提としての基盤の形成を妨害しているものにほかならない。
第6 おわりに
以上のとおり、わが国の死刑制度とその運用には、死刑制度そのものについての存廃の意見とは別に、司法的刑罰制度の観点からみて多くの重大な問題点が存在するのであり、我々法律実務家は、死刑存廃論の立場を超えて、早急に具体的な改革を行うための行動を起こすべきである。
以 上
 奈良弁護士会
奈良弁護士会