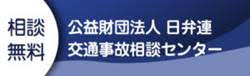会長 相良 博美
被告人ゴビンダ・プラサド・マイナリに対する強盗殺人被告事件において、被告人は一審東京地方裁判所で無罪判決を受けていたが、東京高等検察庁はこれに対し控訴の申立をするとともに職権による勾留状の発布を要請し、東京高等裁判所は、平成12年5月8日、被告人に対する勾留を決定した。これに対し、弁護人は特別抗告をしたが、最高裁判所は6月28日までに特別抗告を棄却する決定をした。
一審判決は、2年余りにわたって合計34回の公判を行い、慎重かつ十分な証拠調べの下に無罪の判決を下したものである。しかしながら、東京高等裁判所は、一審の判決内容について、何らの実質審理をも行うことなく、すなわち、当事者の意見を聞くことも、自ら証拠調べをすることもなく、わずか7日間記録を読んだだけで、被告人に「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があると一審無罪判決を否定する判断をしているのである。また、最高裁判所も「罪を疑うに足りる相当な理由がある場合で、逃亡などの恐れがあれば一審が無罪を言い渡しても記録などの調査により被告人を勾留できる」と述べ、高裁での審理の段階を問わず記録の検討だけでも被告人を勾留できるとの判断を示した。
このような東京高裁及び最高裁の判断は、無罪判決の場合はもちろん、刑の執行猶予等の裁判の告知があった場合においても、勾留状はその効力を失う旨を規定し、無罪判決後の身柄拘束についてより一層慎重な判断を要求する刑事訴訟法第345条の趣旨に真正面から反するものである。また、一審判決の記録を読むだけで勾留を認めるのは、一審判決を軽く扱うもので不当である。
東京高検、東京高裁及び最高裁が被告人の身柄拘束に固執する実質的理由は、本件被告人は釈放されると同時に強制退去させられることから、控訴審終了まで被告人の帰国を阻止しようという点にある。しかし、強制退去の阻止を目的とする勾留という制度は現行法上のどこにも存在せず、これが憲法および刑事訴訟法の身柄拘束手続に正面から違反することは誰の目にも明らかである。そもそも、強制退去の阻止については、出入国管理及び難民認定法の整備の問題であって、その不備を補うために刑事訴訟法の勾留を用いることを許せば、被告人は強制退去阻止の目的を越えて国内における自由すら剥奪されてしまうのである。
本勾留決定は、無罪の判決を得た被告人を正当な目的も法律上の根拠もなくして拘束するものであり、我々は断じてこれを許してはならない。
 奈良弁護士会
奈良弁護士会