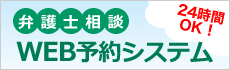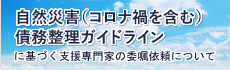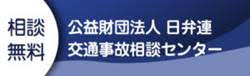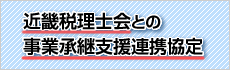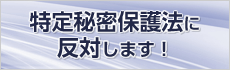- 厚生労働大臣は、2025年(令和7年)6月頃、中央最低賃金審議会に対し、2025年度(令和7年度)の地域別最低賃金額の改定の目安についての諮問を行う予定となっており、例年通りであれば、7月には、その答申がなされる見込みである。
これを受け、奈良地方最低賃金審議会においても、同年度の奈良県の地域別最低賃金に関する審議がなされ、奈良労働局長によって最低賃金額が決定される。 - ここで2024年度(令和6年度)の奈良県の地域別最低賃金であるが、時間給986円とされている。この金額は、前年度から50円の引上げとなったものの、全国の加重平均である1055円を大幅に下回る実態は放置されたままである。仮に時間給986円で月に173.8時間働くとしても、月額17万1367円の収入に留まる。このような最低賃金の水準では、貧困の解消、労働者の生活の安定や向上を図る上で不十分であり、事業の公正な競争を確保することも困難である。
また、同年度における周辺府県の地域別最低賃金は、大阪府が1114円、京都府が1058円、滋賀県が1017円、三重県が1023円と、いずれも、奈良県の地域別最低賃金を大幅に上回っており、あいかわらず周辺府県との格差の問題も解消されていない。 - 上記の地域間格差の是正の必要に加え、昨今、米をはじめとする食料品や光熱費等の生活関連品の価格は急上昇している。2025年(令和7年)4月18日付総務省の報道資料によれば、2024年度(令和6年度)の全国消費者物価指数は、2020年度(令和2年度)に比べて、食料品全体が20.0パーセント、生鮮食品は28.0パーセント、光熱・水道費は14.9パーセント上昇している。
労働者の生活を守り、経済を活性化させるためには、このような物価の上昇をひとりひとりの労働者の賃金に反映させるという意味において、大企業だけでなく全ての労働者の実質賃金の上昇又は維持を実現する必要があり、そのためにはまず最低賃金額を大きく引き上げることが何よりも重要である。 - 他方で、最低賃金の引き上げは、労働者を雇用する中小企業にとっては、人件費の増加による経営負担の増大をもたらす。最低賃金引き上げに伴う中小企業への支援策について、現在、国は「業務改善助成金」制度による支援を実施している。しかし、その支援は未だ十分とは言い難く、日本の経済を支えている中小企業が、最低賃金を引き上げても円滑に企業運営を行うことができるよう十分な支援策を講じることが必要である。例えば、社会保険料の事業主負担部分を免除・軽減すること、原材料費等の価格上昇を取引に正しく反映させることを可能にするよう法規制することなどの支援策も有効であると考えられる。
例えば、高知地方最低賃金審議会においては、地域別最低賃金の引き上げの答申とともに、最低賃金の引き上げによって、影響を受けることの多い中小企業に対する支援にかかる施策について言及している。奈良地方最低賃金審議会においても同様に、積極的な意見を述べるべきである。 - 徳島県においては、最低賃金額が、2023年度(令和5年度)の時間給896円から2024年度(令和6年度)の時間給980円に大幅(84円)に引き上げられた。これは、目安額(50円)に比べて34円高い引上げ額であるとともに、隣接他府県に比べて、25円以上高い引上げ額である(引上げ額は、香川県が52円、愛媛県が59円、高知県が55円となっている。)。徳島県において、このような引上げが実現されたのは、最低賃金の地域間格差の解消に向けて、徳島県をはじめとした地域行政が積極的に取り組んだ結果であるといえる。同県は、具体的には、「徳島県賃上げ支援事業」や「徳島県賃上げ応援サポート事業」等によって、賃上げを行った事業者等に対して、一時金や助成金の上乗せ支給等の支援を行っているが、奈良県においても、最低賃金の引上げに向け、同様の、あるいはそれ以上の支援を行うことで、目安制度に縛られない大幅な最低賃金の引き上げが可能はずである。
- 以上のとおり、奈良県における最低賃金の引き上げは急務である。周辺府県との格差を少しでも是正する必要があることからすれば、本年度の地域別最低賃金は、時間給1035円(前年度の最低賃金の5%程度の増額)を大幅に上回るような引上げがなされるべきである。
2025年(令和7年)6月30日
奈良弁護士会
会長 中西 伸之
 奈良弁護士会
奈良弁護士会