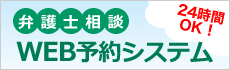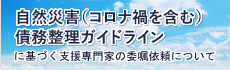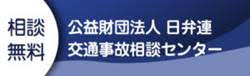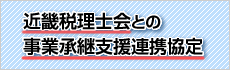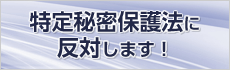-
本年7月18日、名古屋高等裁判所金沢支部(増田啓祐裁判長)は、いわゆる「福井女子中学生殺人事件」について、前川彰司氏に対し、再審無罪判決(検察官控訴に対する棄却判決)を言い渡した。
同事件において、前川氏は、1987年(昭和62年)3月の逮捕当初から一貫して自身の関与を否認しており、確定審第一審の福井地方裁判所は、1990年(平成2年)9月、この主張を認めて無罪判決を下したものの、検察官控訴後の第二審名古屋高等裁判所金沢支部は、1995年(平成7年)2月、関係者供述の信用性を認めて一審判決を破棄し、逆転有罪判決をした。この有罪判決は、1997年(平成9年)11月、最高裁で確定した。
しかし、この確定判決に対し、このたびの再審無罪判決は、主要関係者の一人が自己の利益を図るために前川氏を犯人とする虚偽供述を行い、この虚偽の供述に基づいて捜査機関が他の主要関係者に誘導等の不当な働きかけを行って関係者らの供述が形成されていったという合理的な疑いが払拭できないとして、主要関係者供述の信用性を否定して前川氏を無罪とした第一審の判断が論理則・経験則等に適った正当なものであることが明らかとし、無罪判決を維持し、検察官の控訴を棄却した。
このたびの再審無罪判決は、捜査機関による主要関係者の供述の誘導が実際に行われた具体的な疑いが浮かび上がったと指摘するにとどまらず、職務の公正を保つべき警察官が私的交際関係のない重要証人に対し、証人尋問に近い時期に金銭を交付したとの事実を認定したうえ、公正であるべき警察官の職務に対する国民の信頼を裏切る不当な所為であるとした。さらに、確定審検察官が、主要関係者の供述の信用性判断にとって重要な前提事実について誤りがあることを把握したにもかかわらずこれを秘し、論告や控訴趣意書にて誤った前提事実に基づいた主張を続けたと認定し、このような検察官による訴訟活動については、公益を代表する検察官としてあるまじき、不誠実で罪深い不正の所為と言わざるを得ないとした。そのうえで、このような検察や警察の不正、不当な活動等について、検察や警察に対する信用を失わせるのみならず、刑事司法全体に対する信頼を揺るがせる深刻なものであると判示した。 -
このたびの再審無罪判決の事実認定は妥当なものである。また、警察及び検察の不誠実な対応は、国民の信頼・信用を失わせるのみならず、刑事司法全体に対する信頼を揺るがせる深刻なものであるとの指摘は、極めて全うな指摘であり、当会は高く評価するものである。
したがって、当会は、検察庁に対し、このたびの再審無罪判決に対する上訴権を速やかに放棄し、無罪判決を確定させることを強く求める。 -
ところで、このたびの再審無罪判決及びいわゆる「袴田事件」の再審無罪判決は、かねてより日弁連及び当会が主張してきた再審法改正、すなわち、①再審請求審における検察官保管証拠等の開示命令、②再審開始決定に対する検察官の不服申立禁止、③再審請求審等における裁判官の除斥及び忌避、④再審請求審における手続規定を定める必要性を、改めて明らかにした。
本年6月18日、上記の4項目を含む「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」(以下「本法案」という。)が衆議院に提出され、その後、衆議院法務委員会に付託されて、閉会中審査となっている。本法案は、当会がこれまで求めてきた再審法改正の内容と軌を一にするものであって、高く評価できる。
一方で、再審法改正に関しては、本年4月21日以降、法制審議会刑事法(再審関係)部会において審議が行われ、全14項目に及ぶ多くの論点が提示されている。しかし、このように多くの論点を総花的に検討するのでは、法案化までには相当な期間を要することは明らかで、改正が速やかに進む目処は立っていないと言わざるを得ない。
再審法改正は、何よりもえん罪被害者の速やかな救済に資するものでなければならない。上記4項目は、数多くある論点の中でも、えん罪被害者の速やかな救済を実現する上で極めて重要なものであることから、これらの点については、早急に法改正がなされるべきである。そして、早急な法改正のためには、立法の権限と責務を有する国会において、速やかに本法案を可決すべきである。 -
よって、当会は、検察庁に対し、このたびの再審無罪判決に対する上訴権を速やかに放棄することを強く求めるとともに、国会に対し、速やかに本法案の審議を進め、今秋にも予定されている臨時国会において本法案を可決・成立させることを求める。
2025年(令和7年)7月28日
奈良弁護士会
会長 中西 伸之
 奈良弁護士会
奈良弁護士会