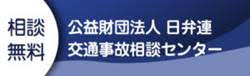(注) 本書は、奈良弁護士会作成の絵本「憲法って、何だろう?」について、奈良弁護士会憲法委員会独自の立場から解説を加えたものです。本書の内容に関する文責は、同委員会限りのものであることをご了承下さい。
【 はじめに 】
今回は、奈良弁護士会作成の絵本、「憲法って、何だろう?」をお読みいただき、ありがとうございました。
日本国憲法が制定されて、60年がたちました。人間で言えば還暦です。
パソコンや携帯電話はもちろん、テレビすらなかった時代に作られた憲法ですから、あちこちから、「もうそろそろ変えよう」という声が出てくるのは、自然なことかもしれません。
しかし、世界史的に見れば、憲法の基本となる考えが誕生してから、300年以上たっています。「フランス人権宣言」などは、200年以上一度も改正されることなく、今でも「現役」として活躍しています。60年経っただけで「憲法は古くなった」というのは、いささか軽率でしょう。
とはいえ、「そもそも憲法とは何なのか」「なぜ大事なのか」ということは、意外なほど、議論されてこなかったように思います。そのためか、学校の授業で教わる「憲法」の内容は、無味乾燥な「暗記物」になってしまっているように思われます。
例えば、学校で習う「日本国憲法の三大原則」、つまり、
- 「基本的人権の尊重」
- 「国民主権」
- 「平和主義」
は、なるほど、大事な特徴です。
しかし、それだけでは、憲法の一番大事なところはわかりません。この「三大原則」の下には、もっと本質的な「基本理念」ともいうべき考え方があります。それは、「個人」と「法の支配」という2つの理念が融合してできた「立憲主義」という思想ですが、「憲法を変えよう」という人も、「変えてはいけない」という人も、その内容を知らないままに議論をしているように思えます。だから、余計に、「憲法」が難しくなってしまうのです。
では、この「一番大事なところ」を、どうやったら皆さんに理解していただけるだろうか…いろいろ考えた末に、つくってみたのがこの絵本…「憲法って何だろう」です。
私達は、「どうせわかりやすくするのなら、中学生にもわかってもらえる内容にしよう」と思いました。
そのために、「絵本」という体裁にして、憲法を「勉強」するのではなく、「感じる」ことができるように工夫してみました。今回の作業にボランティアで協力していただいた星野さんのイラストは、そのイメージをさらに豊かに膨らませてくれるように思います
もし、皆さんが、この冊子を読んで、「ええっ、憲法には、こんなことも書いてあるの?」と驚いていただけたのであれば望外の喜びです。
さて、ここでは、この「絵本」を題材に勉強会をされたり、これを授業の教材に使おうとされる方々のために、「解説」を用意してみました。ぜひ、ご一読の上、ご感想をお寄せ頂ければ幸いです。
あなたは、あなたの人生の主人公
13条 「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
私達の憲法は、全部で103条の条文からできています。では、その中で「一番大事な条文」はどれでしょうか? …これを聞くため、全国の中学生・高校生相手にアンケートを取ってみたら、一体、どんな答えが返ってくるでしょうね。
「9条」でしょうか、「前文」でしょうか、それとも「わかんない」でしょうか…。ぜひ知りたいところですが、「13条」と答える学生は、ほとんどいないと思います。
しかし、実は、この条文こそ、私達の憲法の一番大事な条文の一つなのです。
この条文には、「すべて国民は個人として尊重される」と書かれています。「個人が尊重される」ではなく、「個人として」尊重されると書かれています。普通の人は、改まって「あなたは個人ですね」と言われても面食らうでしょう。では、「個人として」尊重されるということには、どういう意味があるのでしょうか。
実は、「個人」という言葉は、江戸時代までの日本にはありませんでした。これは、西洋から来た “Individual” (インディヴィジュアル)という言葉の訳語です。明治時代の先輩達が四苦八苦して作りだした言葉なのですね。残念ながら、まだ、完全に日本人の価値観に溶け込んでいない。だから、わかりにくいのです。
とはいえ、ヨーロッパでも、Individualという言葉の歴史は古くありません。これは、いわゆる「近代」という時代になって登場した価値観を反映した言葉です。だから、この言葉の意味を知ろうと思えば、近代以前の社会、つまり「中世」と呼ばれる時代を勉強するのが一番の近道なのです。
そこで調べてみますと、近代になるまで、ヨーロッパでも日本でも、一人一人の人間は中世的な「オキテ」、つまり「身分」や「家」や「領地」などに、がんじがらめにされていたことがわかります。好きな職業についたり、好きな人と結婚したり、好きなところに住むことなど許されなかったのです。
そして、この中世的な「オキテ」をうちやぶる人間像こそが、Individual「個人」だったのです。そこには、「自分は自分だ」「自分が自分の人生の主人公だ」という決意が込められているのです。
このことを、「絵本」では、
- 「あなたは、あなたであるだけで、大切な人」
- 「あなたは、誰のものでもない」
- 「あなたは、どこに住んでもかまわない」
- 「あなたは、どんな仕事についてもかまわない」
- 「あなたは、誰と結婚してもかまわない」
- 「あなたはほかの人にめいわくをかけなければ自分で自分の生きがいを見つけて自分の人生を歩むことができる」
- 「それが自由です」
と表現しました。
「そんなのあたりまえじゃないか」と思われる方がいるかもしれませんが、歴史的に見ると、決してそうではありません。現代社会にあっても、このような価値観に反する生き方を余儀なくされている人たちはたくさんいるのです。
そのように考えると、憲法が「自由」を保障することの意味もおわかりいただけるでしょう。<br>
13条は、それを「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」を「国政の上で最大の尊重を必要とする」と表現しています。つまり、誰もが、「個人」として、自分で自分の生きがいを見つけて、自分の人生を歩むことができるような社会をつくること…それこそが、私たちが日本という国を作っている最大の目標なのです。
さて、13条には「公共の福祉に反しない限り」という言葉があります。条文を見ればわかるように、「公共の福祉」というのはわが憲法が認める唯一の人権制約原理です。ですから、これを広く解するか狭く解するは、人権保障のあり方を根本的に左右する大問題なのです。
ただ、「公共の福祉」という言葉の意味を、国語辞典を引いただけで理解できる人はまずいないでしょう。
なぜかというと、戦前の日本には、「公共の福祉」の語源となる “public welfare” に相応する言葉がなかったからです。基本的人権の保障すらなされていなかったところに、その適正な制約について共通の認識がなかったのは当然で、ぴったりあてはまる「わかりやすい」日本語などありません。明治の人達がIndividualを「個人」と訳し、意味を理解するまで悪戦苦闘したように、戦後の私達は、「公共の福祉」という言葉とその中身を受け入れなければならなかったわけです。
では、この点について学者がどう考えているかというと、現在、通説となっているのは、「公共の福祉」を「基本的人権相互の矛盾・衝突を調整する公平の原理である」と解釈する考えです。つまり、人権を制約することはあっても、それは「個人」相互の調整のレベルにとどまる…という考えです。裏返せば「お国のため」という価値観を排除するという共通の理解がある。問答無用の「国益」とか「そんなことをする奴は非国民だ」という論理は認められないのです。
一般の方には少しわかりにくいでしょうから具体的に言いますと、いくら「表現の自由」があるからといって、他者のプライバシー権や名誉権を無視してはいけない…これが「個人相互の調整」です。他方、戦前のように、演説会を憲兵が監視したり、「戦争反対」というだけで逮捕されるようなことがあってはならない。それは、「お国のため」に表現の自由を規制することを憲法が許さないからなのです。
ところが、この言葉を、「公益」とか「公の秩序」と読みかえる人がいます。そういう人たちは、「その方がわかりやすい」というのですが、どうでしょうか。なるほど、言葉としては「わかりやすく」なるかもしれません。しかし、それは戦前からある言葉だからです。つまり、意味も戦前のレベルに戻る。そこへ、戦前からある「国家あっての個人」という考え(これについては後で説明します)が結びつくと、今まで憲法学者が一生懸命に排除してきた「お国のため」の論理が憲法に持ち込まれてしまいます。そうなれば、国民は、自分の人生の主人公ではない。もはや、「個人」ではなくなってしまうことになります。
実は、戦争中の日本で支配的だったのは、このような考えでした。当時、「非国民」という言葉がありましたが、これは「国のために生きる(死ぬ)」ことを拒否した「個人」が、人間として扱われなかったことを意味します。しかし、そのような考えが支配的なところに「自由」や「基本的人権」など入り込む余地はありません。だからこそ、「公共の福祉」という言葉の本来の意味を、しっかりと理解する必要があるのです。
みんなが、自分の人生の主人公
14条1項 「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
2項 「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」
先程の説明で「自由」の意味をイメージしていただいたと思いますが、この「自由」とワンセットで語られることが多いのが「平等」です。歴史的に見ると、「平等」とは、まず第一に、「身分」の否定を意味しました。お侍だろうと百姓だろうと同じ人間、その価値に差はない…という訳です。
では、侍や貴族というものがなくなった現代にあって、「平等」を保障することに、どんな意味があるのでしょうか。
「みんな同じに扱う」ということでしょうか。でも、実際には一人一人みんな違いますね。特に、最近は「みんなが一等賞になれるはずがない」「頑張った人もそうでない人も、みんな平等ではおかしい」「平等を実現するのは不可能だ」といった声も多く聞かれます。だとすれば、もはや「平等」という考えは時代遅れになってしまったのでしょうか。
確かに、人間は皆一人一人違います。痩せた人もいれば、太っちょの人もいる。足が速い人もいれば、絵をかくのがうまい人もいます。ですから、それをみんな同じに扱うと、おかしなことになってしまいます。
しかし、憲法のいう「平等」とは、人それぞれに「違い」があることを否定するものではありません。
それぞれに「個性」があることを踏まえた上で、「人間としての価値」を同じものとして扱わなければならない…というのが憲法のいう「平等」なのです。
そして、「人間としての価値が同じ」とは、先程説明した「誰もが個人として尊重される」ということの裏返しです。つまり、誰もが等価値な「個人」である…みんなが自分の人生の主人公となって、生きがいを持つことができる…こういう状態こそが、憲法が保障する「平等」なのです。
このことを「絵本」では
- 「みんな、違う顔をしている」
- 「でも、みんな、その人であるだけで、大切な人」
と表現しました。
このように考えると、男女が同じ服を着る必要はありません。皆の給料を一緒にする必要もないし、運動会でみんなを一等賞にする必要もありません。他方、このように考えると、現代にあっても「その人であるだけで大切に扱われていない人」「生きがいを持つことができない人」がいることにお気づきでしょう。
たとえば、能力はあるのに、性別や、特定の身体的障害があるという理由だけで希望する仕事につくチャンスも与えられない人は、差別されています。貧富の格差がひどくなり、才能があるかも知れないのに、お金がなくてそれを伸ばせない人たちが出てくれば、平等な社会とは言えません。
このように見ると、「自由」と「平等」とは根っこの部分で重なり合っていることがおわかりでしょう。
では、なぜ、「自由」と「平等」は別々に保障されているのでしょうか。歴史的に見ると、それには理由があります。
実は、「平等」が保障されることは、次に述べる「国家」というもののなりたちに深く関わっているのです。
なぜかというと、「価値の違う人間」は、「一つの国」を作ることができないからです。「身分」が否定されてこそ、初めて「同じ国家の国民」という意識が生まれ、現代の私達がイメージする「近代国家」が形成されたのです。
このことは、「平等」が保障されない国家がどうなるかを示唆しています。「格差」が進み、同じ国の中で「価値の違う人間」の存在が当たり前になってしまうと、「国家」が空中分解してしまうおそれがあります。
たとえば、「格差先進国」と呼ばれるアメリカでは、「要塞住宅」と呼ばれる、周囲をフェンスで囲い、入口に厳重なゲートをもうけた高級住宅街が増えていると言います。その周囲には貧困層の人達が住んでいますが、「要塞住宅」エリアには一歩も立ち入ることができない。この国では全国民共通の医療保険制度すら存在しないことが知られていますが、わが国でも同じような傾向が進めばどうなるのでしょうか? これは、「格差」が語られる今だからこそ、深く考えなければいけない問題だと思います。
みんなが、日本という国の主人公
前文 「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。」
1条 「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」
20条3項 「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」
「国民主権」という言葉は、ほとんどの人が聞いたことがあるでしょう。しかし、この言葉の意味を正確に説明できる人は少ないと思います。学校では、「国民主権」とは「民主主義」と同じだと教えられているようです。
しかし、両者は、密接に関連はしているものの、同じものではありません。そのことは、「民主主義」は古代ギリシャの時代からあったのに、「国民主権」という言葉は近代になって初めて誕生したことからも、おわかりいただけるでしょう。
では、国民主権…つまり、「主権」が「国民」にあるとは、どういうことなのでしょうか?
実は、憲法を勉強するとき、一番難しいのがこの問題です。それは、「主権」という言葉が、「個人」と同じく、歴史的な理解を必要とする言葉だからです。また、それと関連して、「国民」という言葉の意味も、使う人によって微妙に違うからです。ですから、言葉の意味からしっかり押さえていかなければなりません。
まずは、「主権」という言葉です。これが誕生したのは16世紀のことでした。その意味は、当初「国家の絶対的かつ永久的な権力」などと説明されていましたが、要は、現代の私達がイメージする「国家権力」と同じだと言って良いでしょう。
実は、中世までの世界に、こういうものはありませんでした。「王様」はいましたが、せいぜい、「ムラ」の連合体のリーダー…比喩的にいえば「学級委員長」くらいの力しかなかなったのです。
ところが、中世から近代へと時代がかわり、「ムラ」が解体されてゆきます。その過程で誕生したのが「個人」でした。他方、それまでバラバラに分散していた権力もどんどん集中してゆき、最後には「主権」が誕生します。そして、それを最初に握ったのが、世界史で習う「絶対王」と呼ばれる人達だったのです。
この変化は、日本では、「明治維新」…江戸幕府の「将軍」から日本国の「天皇」への交替…という形で劇的に進みました。ですから、比較的イメージしやすいと思います。
かくして近代となって「主権国家」が誕生します。これは「国民国家」とか「近代国家」と呼ばれることもありますが、これこそ、現代の私達がイメージする「国家」のルーツです。では、この「主権」は、誰に帰属するのでしょうか。
多くの国で、最初、それは「王様=君主」に属すると考えられていました。その理由付けの一つが「国家は神に造られたものであり、君主の権力も神から授けられたものだ」という考えです。これは「王権神授説」と呼ばれる考えですが、これによると、個人の「自由」も君主から与えられたものだということになります。
実は、明治憲法も、この考えに立っています。明治憲法の前文を読みますと、古事記・日本書紀にさかのぼる「国造り神話」を前提に、神の子孫たる天皇がこの国を治めると書かれていることにお気づきでしょう。つまり、君主(天皇)が、日本という国の主人公だった。「臣民」たる国民は、天皇から権利を授けられたという構造になっていたのです。
ただ、これが全く間違いだったとは言えません。
なぜなら、歴史的に見ると、君主に権力が集中する過程で、「個人」が中世的な束縛から解放されていったという側面もあるからです。日本でも、明治維新の結果、人々が江戸時代に比べればはるかに「自由」になったのは間違いないでしょう。
しかし、ある時点で、「君主」の権力と「個人」の自由とが衝突するようになります。
その結果起きたのが、イギリスの名誉革命やフランス革命などの、いわゆる「市民革命」という歴史的事件です。これは、主権が君主に帰属するという考えを否定するものでした。これは、歴史の必然というべきでしょう。
なるほど、「君主主権であっても、君主となる人が本当に素晴らしい能力と人徳を備えていれば、構わないんじゃないか」と思う人がいるかもしれません。しかし、近代になって誕生した「国家」は、「100人の村」ではありません。何千万、何億人という人々が活動する巨大なシステムなのです。これを一人の人間が統治することは、人間の能力を超えている…そもそも不可能なのです。それを無理に行えば、必ずどこかで間違いが起き、個人の自由と衝突してしまうのです。
わが国においても、軍隊が「天皇陛下」の名をかたり、国家権力を暴走させ、無謀な大戦争へと国を導き、大変な犠牲を出したという苦い教訓があります。その際、天皇自身にも責任があったかどうかはともかくとして、天皇が軍隊の暴走を止められなかったのは事実です。これは、明治維新から半世紀を経て、「天皇」が主権者として国家を統治するシステムが機能しえなくなっていたことを物語っています。
では、君主に主権を帰属させることができないのであれば、誰に帰属させればいいのでしょうか。特定の人間に帰属させることができないのなら、「国民」全体に帰属すると考えるしかありません。
ただし、何千万、何億人といる国民が直接権力を行使することはできませんから、国民から国政を信託された代表がこれを行使することになる…これが「国民主権」という考えです。
憲法前文が「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」と述べるのは、そういう意味なのです(なお、「絵本」では「国民の代表者」を、わかりやすく「リーダー」と表現しました)。
さて、この「君主主権」から「国民主権」への変換の過程で、「国家」と「国民」のイメージも大きく変化します。実は、「国民主権」の議論がとても難しくなるのは、この変化を曖昧にしたまま議論してしまうからなのです。そこで、この点について少し詳しくお話しましょう。
まず「国家」ですが、「王権神授説」では、国家は「神」によって造られたものだと考えられます。そのような考えでは、「国家」とは、単なる人間の集まりを越えた一つの「生命体」のようにイメージされます。そこでの「君主」は「脳」、一人ひとりの国民は「細胞」といったところでしょうか。「細胞」は、一応独立した単位ではあるけれども、それ自体には価値がない。その生命体の一部であるからこそ存在価値があるし、生きてゆけるという訳です。
日本では、この考えは、しばしば「民族」という言葉とともに語られてきました。神話の時代から続く生命体としての「日本国」、そしてそれを構成する細胞としての「日本国民」のイメージを、「日本民族」という言葉で表現していたのです。そして、その頂点に君臨しつづけてきたのが「天皇」であり、それこそがわが国(民族)のアイデンティティ=「国体」であると強調されてきたのです。
そして、現在でも、この「民族」と同じ意味で「国民」という言葉を使う人がいます。そうすると「国民主権」という言葉の意味が、本来のものから微妙にずれてしまいます。そこから導かれる結論は、君主(天皇)主権に近づいていってしまうことに注意しなければなりません。
他方、これと対極にある考えは、「国家」とは、そもそも独立した価値を持つ「個人」がつくった「協同組合」のようなものだというものです。つまり、Aさん、Bさんは、○○国の国民であるとか、○○民族の一員であるとか、そんなことを抜きにして、無条件で独立した価値を持つ「個人」である。ただ、1人で生きてゆくよりも皆で協力して生きていった方が何かと都合がいいので、「合意」(契約)の上で「国家」をつくったという訳です。学校で習う「社会契約論」という考えがまさにこの考えですね。このような考えに立てば、「国民」とは協同組合の「組合員」のようにイメージされます
解されなければならないのです。
さらに、この違いは、より根本的な問題をはらんでいることにも注意してください。それは、「国家あっての個人なのか、それとも、個人あっての国家なのか?」という問題です。
先ほどから述べているように、「個人」も「国家」(国家権力)も、近代という時代になって登場した二卵性双生児のような存在です。だから、どちらが偉いのか…つまりどちらが価値の根元なのかが問われることになります。「国家こそが価値の根元である」と考えるのが「国家主義」、「個人こそが価値の根元である」と考えるのが「個人主義」なのですが、そのいずれを取るかが常に問われるのです。これこそが、憲法の根本問題だと言っても過言ではありません。
先ほど紹介した国民を国家という生物の「細胞」のように考える立場では、おのずと、「国家あっての個人」(国家主義)という考えになります。そうすると、「国家の利益を守るためには、個人を犠牲にしても構わない」という考えにつながってゆきます。戦前・戦中の日本で「お国のために死ぬ」ことが最高の名誉・幸福とされたのは、まさに、このような考えの延長です。
しかし、そのような考えと、先ほど紹介した13条の考えは相容れません。「個人」は自分の人生の主人公なのであって、お国のために生きている訳ではないからです。
そのように考えると、「国民主権」が、単に「民主主義」と同義ではない、重要な意味を持っていることがおわかりいただけるでしょう。「国民主権」とは、「個人あっての国家である。それは協同組合のようなもので、個人(組合員)の利益を害するような国家に存在価値はない」という立場…つまり、「みんなが、日本という国の主人公」だという宣言なのです。
このことを、「絵本」では、
- 「あなたは、一人では生きていけない」
- 「だから、みんなと一緒に、日本という国に住んでいる」
- 「この国は、神様がつくったのではない」
- 「誰かのものでもない」
- 「みんなで、日本という国をつくっている」
- 「それが『国民主権』です」
と表現しました。
なお、私達の憲法は、天皇は「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であると規定しています。これは、天皇家が古代日本から連綿と続き、近代国家日本の誕生にも大きな歴史的役割を果たした事実を踏まえてのことです。
ただし、憲法は、天皇に「主権」が帰属しているとは定めていません。「この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」と明確に規定しています。
また、明治憲法にあって「天皇主権」が「神」によって正当化されていたことを踏まえ、今の憲法は、徹底した「政教分離」の規定を置きました。憲法が「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と規定したのは、何よりも、再び「天皇」が神格化され、その名をかたって権力を暴走させる者が登場しないようにするためだったのです。
リーダーは、みんなで選ぶ
15条1項 「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」
16条 「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」
先ほどの説明で、「国民主権」と「民主主義」とは、必ずしも同じものではないということをご理解いただけたと思います。では、「民主主義」とは何なのでしょうか?
実は、いろいろな人たちがいろいろな意味合いでこの言葉を使うものですから、正解はありません。ただ、これは英語の democrasy の訳語で、demos「民衆」とkratia「権力」というギリシア語が語源なのだそうです。ですから、ここでは本来の意味にたちかえり「民衆による政治」「民衆が自ら政治に関与する制度」を意味するものとして話をすすめましょう。
さて、君主主権が否定され、「国民主権」の概念が一般化したのは市民革命の時代です。では、「民主主義」も、同時に広まったのでしょうか? 答えは「YES」であり、かつ「NO」でもあります。
まず、神によって主権を授けられた君主が政治を行うという「君主主権」の考え方と、「民衆による政治」という考えは、根本的なところで相容れません。ですから、「国民主権」が実現することにより、「民主主義」が実現する条件が整ったとはいえるでしょう。
しかし、「国民主権」から、ただちに「民主主義」が導かれたかというと、そうでもないのです。そのことは、ヨーロッパやアメリカにおいてすら、完全な「普通選挙」が実現したのが第二次世界大戦後だったことからも明らかでしょう。「民主主義」という考えが広く支持されるようになったのは、「国民主権」よりもずっと後のことだったのです。
「主権が国民にあるのに、なぜ、政治に参加できないのか?」と思う人も多いでしょう。
しかし、ギリシャ・ローマの時代から、「民主主義」とは、非常に「危なっかしい」政治制度であると認識されていました。しかも、ルソーの影響を受けて史上初の成人男子の普通選挙を実施したフランス革命は、ある意味、大失敗に終わりました。「ギロチン」に象徴されるように、政治的対立の中で、すさまじい数の人々が処刑されたのです。これは、民主主義の「危うさ」を裏づけるものだと考えられました。
かくして、フランス革命後、「民主主義」は積極的に否定されてきた…というのが実情でした。国民主権との関係は、「主権は国民に帰属するのだとしても、それを行使するのはあくまでその代表者だ」と説明されてきたのです。
君主主権が否定された後、大きな力を持ったのは立法権を持つ「議会」です。そして、近代と呼ばれる時代にあって、議会の議員となれる人、あるいはそれを選ぶことができるのは、ごく一部の限られた人…男性の高額納税者だけでした。それは、「知識も教養もない庶民や女性を政治に参加させると、混乱が起きる」と正当化されていました。
しかし、君主が一人だけで主権を行使できないのと一緒で、一部のお金持ちだけが「国民の代表者」として主権を行使するのにも無理があります。どうしても、自分達だけに都合のよい政治をしてしまうのは避けられません。
そうすると、なぜ、この人達が「国民の代表者」といえるのかが問われるのは当然です。
また、「持つ人」と「持たざる人」との間で、「国民の代表者」を選ぶ手続に参加できるかどうか差が出るのは「不平等」ではないか?…という疑問も出てくるでしょう。
かくして、「普通選挙運動」が各地でまきおこり、「民主主義」を認めざるを得ない時代がやってきます。具体的には、貧富の差や性別を問わず、「選挙権」「被選挙権」「請願権」が権利として保障されるようになり、それらが「参政権」として憲法上の権利として承認されるようになったのです。
このことを、「絵本」では
- 「この国のリーダーはみんなで選ぶ」
- 「神様が決めるのではない」
- 「誰か一人が決めるのでもない」
- 「あなたは、リーダーに直接お願いすることができる」
- 「『自分がリーダーになる』と名乗りをあげてもいい」
- 「それが『参政権』です」
と表現しました。
ただ、現在の憲法の定める制度は、「国民の代表者」を通じて政治に参加する「間接民主主義」と呼ばれるものです。
主権が国民にあるのならば、いっそ、国政のすべてにわたって、国民が直接的に政治に参加する「直接民主制」を実現すべきではないか?…と考える人も多いのではないでしょうか。
しかし、そう結論づける前に考えなければならないことが2つあります。
1つは、憲法の目標は、誰もが自分の人生の主人公となり、生き甲斐を追求できる社会を実現することであって、民主主義はあくまでその手段に過ぎないということです。
もう1つは、一口で「国民」といっても、皆、違うということです。一人ひとり違う個性を持った「個人」が何千万人、何億人と集まったのが「国民」なのです。それを忘れて「みんなで政治をする」ことに、危なっかしさが伴うことを忘れてはいけません。
数が大きくなればなるほど、きちっとした議論がしにくくなる。荒っぽい多数決が横行する…そんなことを経験したことはありませんか。本当の「協同組合」であっても、組合員が何百人、何千人となれば、「総会」だけで全部を決めるのは無理です。それを無理に行おうとすれば、荒っぽい多数決が横行してしまいかねません。それが、もし、国の政治で起きたらどうなるのか。例えば、一時の政治的熱狂の中で、「○○民族の血を引いている者は財産を没収して収容所に隔離する」といったルールがポンと決められてしまう危険性は、直接民主制を採ったからといって防げません。荒っぽい多数決によって利益を得るのは「多数者」だけです。それによって犠牲になる少数者はたまったものではありません。
では、この「多数者の暴虐」を防止するにはどうしたらよいか…これこそが、「民主主義」を取り入れることによって現代憲法が背負い込むことになった大きな課題の1つなのです。
そして、その課題に対する一つの答えが、政治的決定過程における熟慮と討議を保障しなければならないという考え方です。憲法改正などの一部の重要事項を除き、通常の政治意思決定は、皆から選ばれた代表者が行った方が、熟慮と討議を重ねることができるのではないか。それが、私達の憲法が直接民主主義を採用しなかった理由なのです。
じっくり考えて、議論するのが大事
1条1項 「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」
参政権が保障され、「国民の代表者」をみんなで選んだとしても、それだけでは、13条が目ざす政治が実現するとは限りません。形だけ普通選挙が実施されていながら独裁者が支配し、自由が蹂躙されている国は、過去も現在も存在します。
考えてみれば、選ばれた「国民の代表者」も人間ですから、間違うことがあります。自分にだけ都合のいい政治をするかも知れません。自分の地位を守るため、大事な事実を隠したり、積極的に嘘をつくかも知れません。
ですから、「国民の代表者」に選ばれなかった国民一人ひとりも、国家のありかたについて必要な知識・情報を身につけ、じっくり考え、その意見を交換するための議論をし、その上で参政権を行使しなければなりません。また、それをより積極的に行うため、「集会」を開いたり、「結社」(政党)をつくっていく必要があります。
つまり、憲法21条1項で保障された「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」は、単に国民一人ひとりにとって大事であるばかりではく、民主主義を実現する上でも必要不可欠なものなのです。
裏返すと、参政権を保障するだけでは民主主義は機能しないということです。例えば、戦前・戦中の日本でも選挙は実施されていましたが、「治安維持法」のために、民主主義は正常に機能しませんでした。国民は「戦争反対」と口にすることすら許されず、莫大な犠牲を避けることができなかったのです。
このことを、絵本では、
- 「みんなでつくった国だから」
- 「選ばれたリーダーにお任せではだめ」
- 「一人一人の国民が」
- 「じっくり考えて」
- 「議論する」
- 「それが『民主主義』です」
と表現しました。
ただ、理想の「民主主義」を実現するのは簡単なことではありません。これは、日本のみならず、世界中の国にとって永遠の課題であると言ってもよいでしょう。
例えば、民主主義の運営にあたり必要不可欠な「政党」を例に取ってみても、理想と現実との間には大きなギャップがあります。現代日本において、政党の党員となっている人はむしろ少数です。その政策を知る人も少ない。選挙もその延長線上で行われますから、金権選挙になったり、イメージ選挙になったりしがちです。金がかかってしかたがない。そのため、「政党を保護するため」と称して国から助成金が支給されていますが、これは任意「結社」たる政党の本来の姿とは、いささか異なるものだと言わねばなりません。同時に、政党への「企業献金」は、その政策が、国民一人ひとりの熟慮と議論を踏まえてのものとなりうるのか?…という問題を生み出します。
また、最近は、「政党の要件を法律で定めるべきだ」とする意見まで出ています。その多くは、「税金から助成金を出す以上、どんな団体にも出すわけにはいかない」というもので、一見すると、スジが通った議論です。しかし、ひとたび政党の資格を法律で制限することが認められれば、「国民の代表者」は、自分を批判する団体を政党と認めず、国政への参加を許さないという誘惑にかられることになります。20世紀末に崩壊したソ連型社会主義国家では「共産党」以外の政党の存在が禁止され、独裁政治が続けられました。その過ちを繰り返してはなりません。
ただ、このような意見が出てくる背景には、国民の政治への関心が薄く、任意の「結社」としての政党がなかなか機能していないという現実があります。つまり、当たり前の事ではありますが、民主主義を機能させてゆくためには、国民一人ひとりが、いかに「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」を積極的に使いこなして行くか、その姿勢が問われているのです。
憲法は、リーダーを縛るもの
98条1項 「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」
第99条 「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」
先ほど、「主権」(国家権力)は近代になって誕生したものだと言いました。その中で最も重視されていたのは「立法権」です。実は、中世に「立法権」は存在しませんでした。中世ヨーロッパでは「法」とは「慣習法」であり、「当然にある」あるいは「発見」するものだったからです。王様(君主)が「法」(ルール)を「作り」、国民がそれを守る…現代の私達にとってあたりまえの「立法」という作業は、それまでの発想を180度転換させるものでした。わが国でも、日本人全員に適用される「法」は、明治維新とともに、初めて誕生したのです。
その後、「君主主権」から「国民主権」への変化に伴い、立法権の主体は君主から「国民の代表者」(特に「議会」)に変わりましたが、「作られた法(ルール)を全国民が守る」という基本構造は変わりません
そして、その「法」の中には、私人と私人の関係を決める「民法」、プロの商売人同士の関係を決める「商法」、刑罰の対象となる行為を定める「刑法」等々、いろいろなものがあります。
では、「国民の代表者」は、どんな内容の「法」(ルール)も作ることができるのでしょうか。
確かに、「国民の代表者」は、国民から選ばれた人たちです。しかも、「国民主権」の建前からは、13条の目ざす政治を実現するために「立法権」を行使しなければなりません。
しかし、今まで何度も繰り返してきたように、この「国民の代表者」も人間です。間違うこともある。しかも、この「国民の代表者」は、国民の誰よりも強い力を持っています。かつての「君主」同様、警察や軍隊を動かすこともできます。だとすれば、たとえおかしな「法」(ルール)が作られようとしても、それを実力で止めることができる「個人」など存在しません。ただ、それでは、実質的にはかつての「君主主権」と何も変わらないことになってしまいかねません。では、どうすればよいのでしょうか。
実は、ここで重要な役割を果たすのが「憲法」なのです。なるほど、「国民の代表者」より力のある「人」はいません。しかし、「憲法」は「国民の代表者」よりも強い。彼が憲法に違反する命令を出しても、軍隊も警察も動かない。逆に、憲法に逆らった「国民の代表者」が権力の座を追われるのです。
つまり、憲法は、「国民の代表者」によって作られる他の「法」とは違い、「国民の代表者」に優越し、これを縛るルール=「最高法規」なのです。
このように、最高権力者に優越する「法」(最高法規)が存在する…という考えを「法の支配」と言います。
そして、この考えは、憲法98条1項の「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」という規定や、99条の「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」という規定に反映しています。
このことを、「絵本」では
- 「みんな、リーダーの決めたルールに従う」
- 「リーダーは、憲法に従う」
- 「なぜ?」
- 「リーダーも人間だから」
- 「かならず、まちがうから」
- 「たいへんなことになるから
- 「リーダーが決めるルールが『法律』」
- 「リーダーを縛るルールが『憲法』」
- 「それが『法の支配』です」
と表現しました。
しかし、この「法の支配」の理念も、「個人」と同様、その本来の意味が理解されているとは言えません。多くの人達が「法の支配」と「法治主義」とを混同してしまっているのです。
「法治主義」とは、君主主権を取る国々で発達した考えです。わかりやすく言えば、「君主の気まぐれで結論が左右されるようでは国民は安心して生活できない。だから、政治は客観的な法(ルール)に基づいて行われなければならない」という考えで、君主主権の下でも不十分ながら人権保障を実現するにあたり、一定の役割を果たしました。
しかし、「法治主義」の考えでは、憲法も君主が定める法の一つでしかありません。それは、君主を「縛る」ものとはなりえなかったのです。そのことは、戦前の日本における天皇と明治憲法(大日本帝国憲法)の関係を考えればおわかりいただけるでしょう。
これに対し、「法の支配」では、「憲法は最高権力者よりも優先する」と考えます。国民主権の下にあって、最高の権力を持っている「人」は、「国民の代表者」ですが、それよりも「憲法」が優先する。他の法律と違い、憲法は、「国民の代表者」を縛るための「最高法規」であるところに存在価値があるのです。
この点をきちんと押さえていないと、いろいろ混乱した議論が出てきます。
その一例が、「憲法に権利ばかり書かれているのはおかしい。もっと国民の義務を規定すべきだ」という意見です。しかし、国民に義務を課すのは「国民の代表者」が作る「法律」の仕事です。憲法の役割は、その行きすぎを防止するために「国民の代表者」を縛るところにあります。その憲法に「国民の義務を書くべき」というのは、的はずれな議論だと言わねばなりません。
もう一つの例は、「憲法に、私人による人権侵害を禁止する条項を入れるべきだ」という意見です。なるほど、昔から「企業の中に憲法は入らず」という言葉があり、「憲法を私人間にも直接適用すべき」という意見も根強くあります。
しかし、99条は一般の「国民」(私人)に憲法尊重擁護義務を課していません。それは、憲法が「国家権力」を行使する「国民の代表者」を縛る法だからこそです。憲法を「国民」(私人)にも守らせようという意見は、一見すると人権擁護に役立つように見えて、実は憲法の一番肝心な役割を曖昧にしてしまうことに注意しなければなりません。
もちろん、企業を始めとする様々な団体との関係で、「個人」としての生き方が妨げられることがあってはなりません。しかし、それは、個々の「法律」の制定ないし解釈のレベルで解決できるし、解決すべき問題なのです。
リーダーは、1人ではいけない
第41条 「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である」
第65条 「行政権は、内閣に属する」
第81条 「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」
憲法は、国民の「国民の代表者」を縛るものだと言いました。では、具体的には、どのようにして「縛る」のでしょうか? その1つの方法が「権力分立」です。
何度も繰り返しますが、1人の人間が近代国家という巨大なシステムを統治することは不可能です。だからこそ君主主権が否定されたのですが、国民主権の下では、「国民の代表者」が1人である必要はありません。国家の主権作用を複数に分離し、分離した権力を相互に抑制させることによって権力の濫用を防ぐ…これが「権力分立」という考えで、「憲法」が誕生した当初から、憲法の精髄とされてきました。
では、国家の主権作用をどのように分離すればよいのでしょうか。実は、いろいろな方法があるのですが、その中でも特に有名なのが国家の作用を「立法」「行政」「司法」に分離させるモンテスキュー流「三権分立」論です。
彼の論じた命題を紹介すると
第1命題
「同一の執政官または執政官職団に、立法権力が執行権力と結合されると き、自由は全く存在しない。」
第2命題
「裁判権力が立法権力や執行権力と分離されていなければ、自由はやはり存 在しない。」
第3命題
「もしも同一の人間、あるいは主公・貴族・人民の同一の団体が、これら三 つの権力を、すなわち法律を作る権力・公的決定を執行する権力・犯罪や私人間の紛 争を裁判する権力を行使するならば、全ては失われるだろう」
となりますが、
これは、国会に立法権を、内閣に行政権を、裁判所に司法権を付与するという形で、わが憲法にも引き継がれています。
ただし、わが憲法を始め、戦後に制定された憲法の多くでは、裁判所に付与される「司法権」が、「犯罪や私人間の紛争を裁判する権力」以上のものとなっていることに注意する必要があります。それは、モンテスキューの時代に比べ、行政権が突出して巨大になると同時に、「民主主義」と「政党」の登場によって、立法権と行政権との抑止・均衡が働きにくくなったからです。現代の裁判所は、「多数者の暴虐」を防ぎ、少数者の権利を保障するために、立法権を有する国会に対してすら「違憲立法審査権」を行使する権限が認められています。
そのことを、「絵本」では
- 「1人に全部をまかせてはいけない」
- 「ルールをつくる人」
- 「ルールを使って政治をする人」
- 「ルールが間違っていないかをチェックする人」
- 「リーダーは3人必要だな」
- 「それが『三権分立』です」
と表現しました。
さて、現代の「三権分立」が、モンテスキューの時代のそれよりも変化してきたことは、「国家の主権作用を複数に分離し、分離した権力を相互に抑制させる」という権力分立のありかたが、「三権分立」だけにとどまるものではないことも示唆しています。
例えば、かつてのソ連型社会主義国家における共産党「一党独裁」制度を念頭に置けば、「複数政党制の保障」も広い意味での権力分立論の射程に入ってきます。特に、議院内閣制を採るわが国では、多数派の政党(与党)が「国会」と「内閣」の双方の意思決定に深く関与しますから、両者間の抑制・均衡が働きにくいことが意識されなければなりません。そこでは、これを補うものとして、「与党」と「野党」の抑制・均衡が重要な意味を持ってくるのです。
そして、このように考えると、先ほど紹介した「政党の要件を法律で定めるべき」との意見には、権力分立の観点からも重大な問題があることがおわかりいただけるでしょう。なぜなら、「政党の要件を定める法律」は、多数派の政党だけで制定することができるからです。「およそ権力を持つ者が、権力を濫用しがちなことは、万代不易の経験である」という考えによれば、多数派の政党は、常に、対立する「野党」を非合法にしたり、国政への影響力を弱めたいという要求にかられるはずです。それが実現するとき、過大な権力の集中が起きることは避けられないでしょう。
住むところがない人は「自由」?
25条1項 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
先ほど、中世から近代にかけて「個人」という人間観が生まれ、人々は「自由」になったのだと言いました。その時代背景の1つとなったのが、商業・金融活動の発展です。中世的な「ムラ」が解体され、自由な経済活動が営まれる「市場」が誕生してゆく過程と、「個人」individualという人間観が誕生する過程は、密接に重なり合っていたのです。
そして、「個人」とともに、「市場」の主役となったのが「おカネ」(金)でした。通貨自体は昔からあったのですが、社会システムとしての「市場」が登場することによって、事業に投資して収益を上げる…つまり「カネがカネを産む」システムが完成していったのです(ちなみに、「元手になるカネ」のことを「資本」といいますから、これを「資本主義」と呼ぶこともあります)。
このシステムは、画期的な経済システムでした。「ムラ」から解放された人々が「市場」で活躍するということは、数千万人・数億人の人たちが「社会的分業と交換」のシステムの下で活動することを意味します。その上、「資本」となったカネは、自己増殖しようとするパワーを秘めていますから、それが原動力となって、人類史上経験したことがないような爆発的な発展がもたらされたのです。
ただし、何事にも良い面と悪い面があります。「カネがカネを産む」システムは、大きな問題を抱えていました。それは、事業の元手となるカネ(資本)を持つ者とそうでない者との間で、必然的に、「富める者はさらに富み、貧しき者はさらに貧しくなる」…今流に言えば「格差社会」化現象が起きてしまことです。
もちろん、「平等」のところで述べたように、一人一人の収入を同じにする必要はありません。お金持ちはどんどんお金持ちになればいい。しかし、問題の本質は、格差の中で生じる「貧困」なのです。
自給自足のムラと違い、「市場」では、衣食住どれをとってもお金が必要です。それがなければ飢死するしかありません。それを避けるために、極めて劣悪な労働条件で働かざるを得ない人達が沢山出てきます。また、資本(おカネ)の自己増殖パワーは自己コントロールが効きませんから、好景気が続いたかと思えば、不況となって、町に失業者があふれます。市場社会における「失業」とは、単に収入を得る手段がないだけでなく、「社会に居場所がない」ということですから、とても深刻です。
しかも、「貧困」の恐ろしさは、ある一線を越えると、いくら努力してもそこから抜け出せなくなることです。例えば、住むところがなくなってしまった人は、まともな仕事につけなくなり、失業するか、より低賃金の仕事に就かざるを得なくなります。また、その子供は、まともな教育すら受けることができません。かくして、貧困の連鎖が続いてしまうのです。
しかし、このような状態は、憲法13条の目指す社会ではありません。
先ほど、憲法が目指す社会は、誰もが、「個人」として、自分で自分の生きがいを見つけて、自分で自分の人生を歩むことができるような社会であると言いました。ただ、個人がそのような人生を歩むためには、最低限の教育と物質的豊かさの裏付け、そして社会の中での居場所(仕事)が必要なのです。
そのように考えると、絶対的な「貧困」とは「不自由」であり、そのような貧困が放置された状態は「不平等」であると言わねばなりません。それを放置したままでは、「個人」として自由を享受できるのは、一部のお金持ちだけ…ということになってしまうでしょう。
そして、実は、これこそが、19世紀から20世紀前半にかけて「憲法」が行き詰まった最大の原因だったのです。多数の人達が「貧困」(不自由)にあえぐ世の中では、「自由」と「平等」など単なる「キレイゴト」に過ぎないという気分が生まれてきます。かくして19世紀になると、「個人」と「法の支配」という理念の重要性は徐々に忘れ去られ、20世紀になると「ファシズム」と「ソ連型社会主義」という2つの独裁政治が誕生したのです。
このように考えると、13条の目指す社会を実現するためには、何としても「貧困」を克服しなければならないことがおわかりいただけるでしょう。
そのことを最初に憲法に謳ったのが「すべての人に、人たるに値する生存を保障することを目指す」と規定したドイツ・ワイマール憲法(1919年)でした。そして、第二次世界大戦後、多くの国で、同様の政策がとられるようになりました。
そのような流れの中で、わが国の憲法も、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と明記しました(25条1項)。
ここで言う「健康で文化的な最低限度の生活」とは、「個人」として、自分で自分の生きがいを見つけ、自分の人生を歩むことができる生活です。それを下回るような「貧困」(不自由)にあえぐ人をなくし、最低限の教育と物質的豊かさ、そして仕事を確保することは、13条によって国民の「国民の代表者」に義務づけられた課題だと言わねばなりません。だから、25条1項は、そのような生活を営むことを国民の「権利」と規定した上で、より具体的に、「教育を受ける権利」(26条1項)と「勤労の権利」(27条1項)を保障したのです。
また、憲法は、市場社会における「貧困」が、「事業の元手となるカネ(資本)を持つ者」と「持たざる者」との関係によって生じることに着目し、それを修正するために、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他団体行動をする権利」(28条)を保障し、かつ劣悪な労働条件を法律で規制することとしたのです(27条2項、同3項)。
とはいえ、これらが「恩恵」ではなく、「社会的基本権」として承認される過程は、どの国でも単純なものではありませんでした。
なぜなら、それは、「事業の元手となるカネ(資本)を持つ者」の財産権や営業の自由を制約することなしには実現できないものだったからです。
しかし、「貧困=不自由」と考えれば、「貧困」を生み出す事業のありかたは、他人の「自由」を犠牲にして金儲けをすることに他なりません。それは先に説明した(本来の意味での)「公共の福祉」に反します。そのことを明らかにするために、憲法は、わざわざ「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」(29条2項)と規定しているのです。
以上のように考えれば、社会権の保障は、13条の目指す「全ての国民が個人として尊重される社会」を実現するために必要不可欠な権利であることがおわかりいただけるでしょう。
このことを、「絵本」では
- 「学校へ行かせてもらえなかった人は、『自由』」?
- 「働かされすぎて死んでしまった人は、『自由』」?
- 「仕事がない人は、『自由』?」
- 「好きでこうなったわけじゃない」
- 「こういう人たちを助けてこそリーダー」
- 「これは、よわい人たちの権利」
- 「それが『社会権』です」
と表現しました。
もっとも、福祉国家理念や社会権保障のあり方については、現在、各国で「見直し」が進み、「世界的危機」といってよい状況が生まれています。そして、その根拠となる意見は、大きく2つに整理することができるでしょう。
その1つは、「ソ連が崩壊した現代にあって、福祉国家理念は過去のものになった」という意見です。これは、「福祉国家理念」が「ソ連型社会主義」の亜流であるとの認識を前提としています。
なるほど、福祉国家理念が普及するにあたり、ロシア革命(1917年)の影響は絶大でした。しかし、ソ連型社会主義の本質は、資本主義の「否定」…すなわち「生産手段の私的所有」の禁止と「市場経済」の否定にありました。しかし、「市場」は、個人が自由に活動する場でもあります。それを全否定することは、個人の自由をも徹底的に制約することにつながったのです。そのため、これらの国にあっては、「個人」という価値観は「ブルジョワ的」なものとして排斥されていました。それが、この体制が独裁体制に陥り、崩壊していった一因だったと言えるでしょう。
これに対して「福祉国家」理念は、個人が自由に経済活動を行う「市場」の存在も、「資本」の存在も否定しません。ただし、その活動に「貧困(不自由)の発生を許さない」という「公共の福祉」の論理で制約を加えるのです。つまり資本主義を否定するのではなく「修正」してゆこうという訳です。「個人」を否定したソ連型社会主義とは逆に、「個人」という価値観を徹底する方向で「市場」「資本」のあり方をコントロールしようというのですから、根本的発想は逆だと言ってもいいでしょう。
従って、「福祉国家理念」=「社会主義」=時代遅れ…という議論は、いささか乱暴に過ぎると言わねばなりません。
もう1つの意見は、「グローバリゼーションが進み、市場のコントロールなど不可能になった」「そんなことをすれば、かえって市場のエネルギーをそぐ」という意見です。
なるほど、「市場」「資本」の存在を認めつつ、それをコントロールするのは簡単ではありません。歴史的に見て、それが「可能」と認識されるようになったのは20世紀前半…ケインズ理論が登場し、アメリカのニュー・ディール政策が実施された後のことです。
しかし、20世紀の終わりころから「グローバリゼーション」と呼ばれる現象が起き、再び、国家による「市場」「資本」のコントロールが困難になりつつあります。なぜなら、グローバリゼーションとは、「市場」が国境を越えてひろがり、「資本」が「多国籍資本」(多国籍企業)となる現象だからです。もはや、一国だけで「世界市場」や「多国籍資本」をコントロールすることはできません。社会保障を充実させようとしても、多国籍企業から「コストの高い国からは出てゆく」と言われれば、「産業空洞化」が進みます。かくして、わが国だけでなく、アメリカ・ヨーロッパ諸国でも、資本を自国に呼び込み・引き留めるために、競って「新自由主義」的な「規制緩和政策」が取られるようになったのです。
とはいえ、「新自由主義」とは、経済政策としては、修正されないむきだしの資本主義のあり方を積極的に肯定する考えです。従って、それに基づく政策は、必然的に、福祉国家理念の否定と社会権保障の後退を伴い、「貧困」を復活させてしまいます。わが国でも、近時、働いているのに生活保護水準以下の収入しかない「ワーキングプア」と呼ばれる人々や、「ネットカフェ難民」と呼ばれるホームレスが大量に発生しつつあります。彼ら彼女らは、まぎれもなく「貧困」者であり、憲法が予定していない階層だと言わなければなりません。
そのため、憲法改正論の中には「社会保障の主体を、国家から地方公共団体に変えよう」という意見すらありますが、それは、国家の責任放棄と言わねばなりません。財政基盤の弱い自治体では、「貧困」が放置されることが目に見えているからです。さすがに、最近は「格差社会」の問題がクローズアップされ、議論が続いていますが、「産業空洞化」と「貧困」の問題を同時に解決する妙案は見つかっていません。それが、後に述べる「戦争」の問題とならび、「憲法の全面改正」が議論される時代背景となっているのです。
では、どうやって、この「21世紀型貧困」を克服するのか? …実は、これこそが現在の憲法をめぐる最も困難な政治的課題の1つだといってよいでしょう。「昭和恐慌」をきっかけにファシズムと戦争への道を歩んだ戦前の轍を踏まぬためにも、全国民が熟慮と討議を重ねなければならない問題だと思います。
多数決の「いじめ」はダメ
1条 「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」
98条1項 「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」
先ほど、憲法が「最高法規」として「国民の代表者」を縛る方法の1つが「権力分立」だと言いました。しかし、それだけでは十分ではありません。そこで、憲法が取るもう一つの方法は、「国民の代表者」に「全ての国民を個人として尊重する」こと(13条)…すなわち、その「基本的人権の尊重」を義務づけることです(11条)。
それは、憲法が登場した当初にあっては、個人の「自由」と「平等」の保障を意味しました。さらに、20世紀となり、これらと一体のもの、あるいはその前提条件として、「参政権」「社会的基本権」も保障されるようになりました。
ここで気をつけなければならないのは、選挙で選ばれた議員達からなる国会で制定された…つまり、民主主義的な手続を踏んで制定された「法律」(ルール)であっても、個人の基本的人権を侵害することは許されないということです。
確かに、それは多数者の意思を反映したものでしょう。しかし、憲法は「悪法もまた法」という立場は取っていません。
先ほども述べましたが、民主主義は13条の目ざす社会をつくる「手段」に過ぎないのであって、「多数者の暴虐」は許されないのです。少数者…たとえたった1人の基本的人権であっても、それを不当に侵害する法律であれば、それは無効とされます(98条1項)。つまり、「多数決のいじめ」は許されないのです。
このことを、絵本では
- 「『自由』と『平等』そして『参政権』『社会権』」
- 「これは、あなたが生まれながらにして持っている権利」
- 「それが『基本的人権』です」
- 「リーダーも、これを取り上げることはできない」
- 「多数決で決めたルールでもダメ」
- 「それが『人権の尊重』です」
と表現しました。
ただ、「多数決のいじめ」(多数者の暴虐)を防止する制度の設計は、意外と難しいものです。なぜなら、民主主義の実現とともに「多数者」が力を持つようになった「国会」に、少数者の人権保障を期待することはできない。また、「議院内閣制」を取るわが国では、行政権を持つ内閣に国会の立法活動のチェックを期待することもできないからです。そこで、憲法は、最高裁判所に「違憲立法審査権」を付与しました(81条)。
とはいえ、この「違憲立法審査権」のあり方については、いろいろな意見があります。現在の最高裁判所の姿勢は、「具体的な事件の解決に必要な範囲で、判決理由の中でのみ憲法判断を示す」というもので、全体としても、違憲立法審査権の行使には極度に慎重です。現在まで、最高裁が下した違憲判決は10に満ちません。従って、「もっと積極的に違憲判決を出すべきだ」とか、「具体的な事件とかかわりなく法律の合憲性を判断する『憲法裁判所』を創設すべきだ」といった意見が多く出されています。
しかし、問題はそれほど簡単ではありません。なぜなら、選挙で選ばれない裁判官に法律を無効とする権限を与えることには、「非民主主義」的な側面もあるからです。その権限が濫用されては、大きな混乱が生じるでしょう。逆に、合憲判決を乱発しては、ただの「お墨付け機関」になってしまいます。この制度の運用には「基本的人権の保障」と「民主主義」の間の絶妙のバランス感覚が求められるのです。
ただ、「民主主義」の根幹に関わる「表現の自由」の問題については、過去の最高裁判所の姿勢は消極的に過ぎたのではないかという意見が有力です。他の基本的人権の侵害は民主主義的過程で修復される可能性があるのに対し、「表現の自由」の不当な制約が認められれば、民主主義そのものが破壊されてしまい、修復不可能な状態となってしまうからです。
『自由』と『わがまま』は違う
12条 『この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。』
ここまでこの「解説」を読み進められた方は、憲法の根本にある基本理念(立憲主義)とは、突き詰めれば、「個人主義」と「法の支配」という2つの理念であることがおわかりいただけるでしょう。この2つの基本理念をしっかり理解せずに、「国民主権」や「基本的人権の尊重」といっても、ピントはずれな議論になってしまうのです。
しかし、憲法が施行されて60年間、このことが意識されてきたとは言えません。特に、「個人」という概念については、憲法学者ですら、その本来の意味に従って議論するようになったのは、せいぜい、この10年余のことに過ぎないと言われています。
そこで、改めて日本語の「個人」「個人主義」という言葉の使われ方を調べてみますと、「わがまま」というイメージがつきまとっていることがわかります。例えば、「個人プレー」という言葉には、「自分のことしか考えてないやつ」というニュアンスが込められています。そして、そのイメージは、必然的に「自由」という言葉のイメージにも反映しています。<br>
他方、「個人の自主性を重んじる」という言葉遣いもあります、こちらは、積極的・肯定的イメージです。特に最近は、野球やサッカーで「一糸乱れぬ統制」型チームより「選手の個性と自主性重視」型チームが活躍する傾向があって、こちらのイメージも急速に浸透しつつあるように思えます。
では、この「個人」という言葉が持つ「わがまま」と「自主性」という善悪2つのイメージの、どちらがより本質的なものなのでしょうか?これは、非常に難しい問題です。先ほど、「個人主義」か「国家主義」かが「憲法の根本問題」であると言いましたが、近代以降300年以上経ちながら、なおこの問題に最終的な決着がつかないのは、それが、「個人とはいかなるものか」という人間の本質を問う哲学的問題と密接に関係しているからなのです。
実は、この問題は、ヨーロッパでも、300年以上前からずっと議論されてきました。
まず、「わがままな個人」…欲望や感情のおもむくままに行動する「個人」像を前提にすれば、その「自由」とは、そういう個人が「したいことをする自由」「わがままを通す自由」だということになります。ただ、この考えだと、ドロボウも強盗も何でもアリ、最後には殺し合いまで始まってしまいます。「国家」というシステムはあっという間に崩壊してしまうでしょう。
ですから、この考え方は、必然的に、「わがままな個人」を外部から押さえつける「権威」が必要であるとの考えに結びつきます。多くの場合、その「権威」は「宗教」であったり「君主」であったりするのですが、戦前のわが国では、「天皇」と「神」が一体化してこの「権威」とされてきました。現在でも、「天皇制こそ日本国民のモラルの源泉である」という意見が根強く主張されているのはその名残でしょう。 そして、この考えでは、自ずと、「個人」の地位が低まり、「国家あっての個人」(国家主義)という立場に傾斜することになります。
他方、「自主性を持つ個人」…つまり自分の事だけでなく、他人のこと、全体のこともきちんとわきまえて「自律」するモラルを身につけた「個人」を念頭におけば、「自由」とは、「したいことをする自由」ではなく、「なすべきことをする自由」だということになります。そして、このような「個人」と「自由」を前提にすれば、外部からの権威など無用です。宗教や君主の力を借りずとも、「個人」の自主性を尊ぶことで、国家というシステムを運営することができる。従って、この考えは、自ずと、「個人あっての国家」(個人主義)という立場に傾斜してゆくことになるのです。
現代の憲法学にあっても、この問題は「憲法学が前提とすべきは『弱い個人』か『強い個人』か?」という形で議論されています。この議論の対立はなかなか深刻で、どちらが優勢かを一概に論じることはできません。それは、「『強い個人』でなければ憲法は維持できないが、現実の人間はしばしば『弱い個人』である」というジレンマがあるからです。
そういう議論状況の中で、「立憲主義はフィクションである。個人は、そのフィクションに耐えなければならない」という学者もいます。つまり、憲法が想定する「個人」像は、必ずしも実際の人間の姿とは合致しないが、国民は、意識的に「強い個人」となるべく努力し続けなければならない…というのです。
これは、とても重い問題提起だと言わねばなりません。国家主義・君主主権では近代国家という巨大システムを統治しきれないことは歴史的に明らかです。では、個々人が自主性を発揮してこれを支えることができるのでしょうか?…大げさに言えば、これが現代文明を維持しうるか否かを左右するのです。
そして、このように考えると、12条が、自由や権利を保持するためには「不断の努力」が必要なのだと規定していることや、その「濫用」(みだりに使うこと)を戒める理由がわかるでしょう。
憲法は「わがまま」を保障しているのでありません。私達は、自分の人生の主人公となるためにも、「わがまま」と「自由」を、しっかり区別しなければならないのです。
ただ、「弱い個人」か「強い個人」か?…という議論の立て方は、いささか極端に過ぎて、かえって議論を混乱させている側面があるように思えます。実際には「強い個人」もいるし「弱い個人」もいる。否、同じ人間でも「強い」時と「弱い」時があるのです。
だとすれば、本当の問題の所在は、「人間にとっての『幸福』(13条)とは何か」であるかと思われます。
これも、ゲーテ「ファウスト」以来、常に問われ続けてきた哲学的問題ですが、「『一人称の幸福』には限界がある。いくら金持ちになって、城のような家に住み、毎日ご馳走を食べるような生活を送ることが出来ても、それだけでは心の底からの満足は得られないのではないか」というのが一般的な理解だと思われます。
なぜなら、私達人間は、「孤独」を苦痛と感じ、社会をつくる生き物だからです。「幸福」は、他人を押しのけて自分の要求を満たすことだけでは得られない。そのことが人間の価値観として共有されているのだと思います。私達の「絵本」では、13条の「幸福」を「生きがい」と読み替えていますが、それは、他者との関わり合いの中で得られる充足感をも「幸福」の中身としてイメージしてもらいたかったからなのです。
そして、人間が、他者の幸福をも自分の幸福と感じ、人の役に立つことに喜びを感じることができる存在ならば、「強い個人」となることは十分可能です。従って、「立憲主義はフィクション」であるとしても、それは「嘘」なのではなく、努力すれば実現できる「目標」であるということができましょう。
このことを「絵本」では
- 「憲法が保障する『自由』は『したいことをする自由』じゃない」
- 「それは『なすべきことをする自由』」
- 「あなたは他の人をしあわせにすることでしあわせになれる」
- 「他の人の不幸をわかちあって自分の不幸も乗りこえられる」
- 「それが『生きがい』です」
と表現しました。
では、他人とのかかわりの中で「幸福」「生きがい」を見いだすことができるはの人間が、なぜ、「弱い個人」として振る舞うことがあるのでしょうか?
その原因の1つとなるのが「貧困」です。昔から「衣食足りて礼節を知る」という諺がありますが、「貧困」(不自由)に陥った人に他者のことを思いやる余裕などありません。また、明日の食べる物、寝る場所を心配しなければならない人たちが、国政に関する熟慮と討議に参加できるはずもありません。
その意味でも、先ほど論じた「21世紀型貧困の克服」は、憲法の未来を論じるにあたって、避けることができない課題なのです。
もう一つ、個人を「わがまま」に振る舞わせるのが、お金(資本)です。
昨今しばしば新聞をにぎわせる「投資ファンド」は、「ハゲタカ」などと揶揄されることがありますが、ある意味、「資本」の論理に極めて忠実な存在です。顧客から集めた資金を高利回りで運用しなければならない。そうしなければファンド自身が生き残れない。だから、投資先の会社に厳しい要求を突きつける。値上がりで困る人が出るのがわかっていても原油や穀物を買いあさる…それは、しばしば、傍若無人で「わがまま」と評価されかねない行為となります。従って、「市場」の主人公が「個人」となるのか、「お金(資本)」となるかが極めて重要になってくるのです。
しかし、先ほども述べたように、グローバリゼーション…「世界市場」と「多国籍資本」が登場するにつれて、国家ですらその制御が困難になりつつあります。そのことによって、「カネが全て」という価値観が支配的になってきている。しかも、一度は克服されたはずの「貧困」が蘇り、さらに人間を「わがまま」にしてゆく…この悪循環を克服しなければ、「個人の自律」を前提にして成り立つ憲法は、やがて成り立たなくなってしまうでしょう。
何をすべきか…それは自分で決める
19条 「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」
さきほど、憲法の保障する自由とは、「なすべきことをする自由」なのだと言いました。では、個々人が「なすべきこと」とは何なのでしょうか? そのモノサシとなるのは、私達が「モラル」「道徳」と呼ぶものです。その中身を言葉にするのは難しいのですが、その核心にあるのは、先にも触れた「他人の幸せをも自分の幸せとする価値観」でしょう。
さて、そうすると、あなたは、「他の人に何をしてあげればいいのか」を聞きたくなるでしょう。でも、それを他人に聞いてはいけません。なぜなら、それは人によって違うからです。それは、その人の生まれや育ち、社会に占める地位などによって千差万別なのです。その「個性」と「多様性」を大事にしなければなりません。
つまり、「何をなすべきか」「何をするのがいいことか」は、あなた自身が決めること、否、決めなければならないことです。誰か偉い人が決めるものではありませんし、多数決で決めることでもありません。「そいつを殺せ。そうしなければお前を殺す」と言われても、それが理不尽と考えるのなら、断固拒否する。そういう個々人の価値観=「良心」が憲法を支える根元的な力なのだと言えましょう。憲法が「思想及び良心の自由」(19条)を保障したのはそれゆえです。
これに対して、「国家あっての個人」という考え(国家主義)を前提とすると、「なすべきこと」とは「国家に奉仕すること」と同義とされてしまいます。しかも、「国家への奉仕」と「権力者の政策に協力すること」がしばしば同視されます。そのため、「何をなすべきか」「何をするのがいいことか」を「法律」(ルール)で決め、国民に押しつけるということが往々にして行われてきました。20世紀に登場した2つの全体主義…ファシズムとソ連型社会主義のいずれにおいても、徹底した「思想教育」と「思想犯」の取り締まりが行われました。戦前のわが国においても軍国主義的教育が徹底され、「国体護持」という価値観に従わない人は「非国民」として「治安維持法」で処罰されたのです。
しかし、「トップが右を向けば皆右」的な集団は、長期的に見ればもろいものです。トップの判断が間違っていたときには、目も当てられない失敗が起きます。その失敗の最たるものが「戦争」ですが、「なすべきこと」を国民に押しつけた国家が、いずれも、破滅ないし瓦解の歴史を歩んだことを忘れてはなりません。
このことを、「絵本」では
- 「ほかの人に、何をしてあげたらいい?」
- 「何ができる?」
- 「何をすることが『いいこと』?」
- 「それは、みんな違う」
- 「それを決められるのは、あなただけ」
- 「それを、リーダーに聞いてはいけない」
- 「ルールで決めてもいけない」
- 「それが『個性』です」
と表現しました。
ところが、最近は、法律や条例で「何をなすべきか」「何をするのがよいことか」という問題にまで踏み込もうとするものが多くなってきました。
それを反映して、「憲法に愛国心を規定せよ」という意見すら出ています。また、13条の「公共の福祉」を「公の秩序」と書き換えるべきだという主張の中には、「権力者の価値観に反する言動は許さない」という発想が含まれている場合も往々にしてあります。
他方、これに反対する人の多くは、それを「戦争」に結びつけて議論しています。確かに、「思想統制」や「愛国心の強制」の問題と「戦争」とは密接に関連していると思います。しかし、全てを「戦争」「9条」とのみ結びつけて議論すると、より身近な問題を見落とすことになります。
実は、この問題は、日本だけで起きているのはありません。
「経済政策としての『新自由主義』は政治的な『新保守主義』と結びつく」と指摘されることがありますが、福祉国家理念の関係では「小さな政府」となりつつ、精神的自由権との関係では「大きな政府」を目ざす…という傾向は、アメリカなどでも起きていることです。
なぜそうなるかというと、新自由主義的な政策を取ることによって起きる「貧困」(不自由)は、「お国のため」という論理でしか正当化できないからです(それはしばしば「国際競争力の強化」という言葉で語られます)。また、「平等」に関連して述べたように、「貧困」が一般化し、「格差」があたりまえのものになってしまえば、一つの「国民」、一つの「国家」であり続けることが難しくなってきます。そこで、精神的な面で統制を強め、国家としての統一性を保つ必要が出てくるのです
しかも、複雑なことに、「新自由主義」を推進する側ばかりでなく、それに批判的な立場からも、しばしば精神的統制の必要性が説かれます。それは、「新自由主義」的風潮の原因を「個人のモラルの低下」と捉えてしまうからなのですが、このような人たちは、「モラルを備えたエリート」による政治を強調し、国民(特に子供)に対して「モラルを上から押しつけること」を積極的に推奨するようになります。
しかし、問題の根本は、先ほどから何度も触れている「21世紀型の貧困」の克服にあります。それを無視して精神論だけを振りかざしても問題の根本解決はできません。例えば、今、日本の「国際競争力」にとって、最大の脅威は「少子化」だと言われていますが、その背景には「子育て世代の貧困」の問題があります。
それを精神論で乗り切ることは不可能でしょう。
ただ、このような精神的統制の危険性は多くの人が気づいていることですから、これを露骨に主張する人はむしろ少数です。それは、しばしば、「伝統」や「文化」という耳障りのよい言葉を使って主張されることが多いことに注意しなければなりません。「武士道」という言葉が流行したこともありますが、これもその一種でしょう。
確かに、正面切って「伝統や文化を大切にしよう」と言われれば反対しづらいものです。また、「漢方薬」ではありませんが、人間の頭の中で作られたイデオロギーと違って、自然の風土や歴史に根ざして形成された「伝統」や「文化」ならば「副作用」も少ないと思われがちです。
しかし、気をつけなければいけないのは、これらの「伝統・文化論」も、「何が伝統で、文化であるか」とか、「良い伝統と悪しき伝統の区別」という形で、主観的な価値判断を包含せざるを得ないという点です。確かに、むやみに「伝統」や「文化」を否定することは感心できませんが、何が日本の伝統・文化であるか、そのうちの何を後世に伝えるべきであるかという判断は、極めて主観的なものであり、一人ひとりの個人の判断に委ねられるべきものなのです。
そこで、改めて憲法改正問題と関連して主張される「伝統・文化」論の中身を調べてみると、概ね、その「最大公約数」となっているのは「万世一系の天皇制」であることがわかります。そして、その前提に「国家あっての個人」(国家主義)という価値観があることが多いのです。
私達が「伝統」や「文化」あるいは「武士道」という言葉に親近感を感じるのは、不安定な時代に安定と安心を求めたいという無意識の願望があるからでしょう。
しかし、繰り返しますが、私達は「個人」としての自覚と責任を持ち、自分の頭で、「自分が何をなすべきか」という問題に立ち向かわなければならないのです。それは苦しいことではありますが、それこそが憲法の求める「不断の努力」なのだということを忘れてはなりません。
世界には190以上の国がある
前文 「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる」
ここまでは、近代になって登場した「個人」と「国家」を中心に話をすすめてきました。
しかし、世界に「国家」は沢山あります。異なる「国家」と「国家」の関係は、憲法を考えるにあたっても極めて大事なことなのです。そもそも「国家」の精神的支柱となっている「国民意識」も、しばしば、他国との関係で形成されてきました。わが国においても、アメリカからの「黒船」来航という事件がきっかけとなって、「我ら日本人」という意識が芽生えたのです
ただし、「近代」と呼ばれる時代にあっては、この国家と国家の関係は、基本的人権に関係する問題として十分意識されることはありませんでした。
そのため、現代の我々の目から見ると、2つの重大な問題が未解決のまま放置されていました。
その1つは、「植民地」の問題です。大航海時代以降、ヨーロッパ各国は、競ってアジア・アフリカ・アメリカ大陸に進出して自国の支配下に置き、経済的収奪の対象としました。これらの植民地は、他国との関係では本国の領土とされながら、本国との関係では他国であり、その住民は法的保護の対象とされませんでした。
19世紀後半の国際法の教科書には、「国際法は、未開の人類に対して、あるいは野蛮な人類に対してすら適用されてはならない」と書かれていました。その根底にあるのは、「野蛮人に人権などない」という差別意識と、これらを「近代化」するのが文明国の義務であるという歪んだ使命感だったのです。
ちなみに、前述の国際法教科書で日本人は「野蛮な人類」に分類されていたのですが、その日本も、アジアでの植民地獲得に乗り出します。例えば、日本の朝鮮支配は、典型的な植民地支配の一つだったと言えるでしょう。1910年に日本は大韓帝国を正式に日本の一部としましたが(日韓併合)、「朝鮮人」に日本人と同様の権利が与えられることはありませんでした。つまり、多くの近代国家は、植民地の住民の犠牲の上に繁栄を続けていたのです。
それは、近代史の「影」の部分として記憶されなければなりません。
もう1つは、「戦争」です。これについては後で詳しく述べますが、「国家のために人を殺す」戦争は、人権侵害の最たるものです。しかし、20世紀となり、2度の世界大戦を経験するまで、「戦争」と「人権」の問題が結びつけられて考えられることはありませんでした。
しかし、植民地の争奪戦が近代国家同士の大戦争へとつながったことや、第二次世界大戦が「反ファシズム」を大義として戦われたことは、「立憲主義の国際化」ともいうべき現象をもたらしました。
植民地支配の問題については、国連憲章で「人民の同権及び自決の原則」(いわゆる民族自決権)が確認され、それまで植民地とされていた地域にナショナリズムの火をつけました。その結果、多くの新たな国家が生まれ、国連総会でも大きな発言力を持つようになりました。ソ連崩壊後に独立した国家を含め、現在では190以上の国が国連加盟を果たしていますが、国家と国家の関係は、少なくとも建前としては対等であるとされています。
これは、植民地支配が当然だった100年前とは大違いです。
また、「戦争」の問題についても、後に詳しく説明するように、第一次世界大戦後の「戦争放棄に関する条約」、第二次世界大戦後の「国連憲章」制定と、国際法による「戦争違法化」の流れが確実に進んでいます。
その流れの中で、かつて植民地支配と大戦争の当事者であったわが国も、憲法の前文に、「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる」と明記することとなったのです。
このことを「絵本」では
- 「この国に住んでいるのはあなただけではない」
- 「この世界に住んでいるのは日本人だけではない」
と表現しました。
ただし、第二次世界大戦後に制定された「国連憲章」の理想は、米ソ対立と東西軍事ブロックの対立(冷戦)によって、約半世紀にわたり、実現が困難な状況にありました。その後、ソ連は崩壊し、冷戦も終結したのですが、アメリカが国連と一線を画そうとしていることもあって、新たな世界秩序の構築は模索の過程にあります。
他方、グローバリゼーションや、地球温暖化への対応等、一つの国家では対応しきれない新たな課題も次々と生まれてきています。こういった中で、日本が果たすべき役割は何なのか?…これも、今後、私たちが熟慮と討議を重ねていかなければならない問題でしょう。
争いごとで、「戦争」はしない
第9条1項 「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」
世界中に190以上も国があり、それぞれが国際社会で活動していれば、必ず、どこかで、「国益」と「国益」とが衝突します。つまり、「国際紛争」は必ず起きる。そのこと自体は、どうやっても防ぐことは出来ません。
隣接する国どうしでは国境線をめぐる問題が起きるでしょうし、石油や天然ガスなどの天然資源をめぐっては、どの国も利権を確保したがります。最近では環境汚染の問題も国際化し、もめごとのタネとなるようになりました。
問題は、この「国益の衝突」=「国際紛争」を解決する手段として「戦争」が認められるかどうかです。
近代になって「憲法」が誕生した当時、かろうじて戦争の制限を説くのは、中世以来の「正戦論」のみでした。
しかし、その主張は「戦争には大義名分が必要である」という程度の意味しか持ちませんでした。
やがて、19世紀になると、その考えすら放棄されます。世界各地でヨーロッパ列強国による「野蛮人の近代化」=植民地獲得のための戦争が進められたこともあって、「無差別戦争観」という考えが支配的になります。つまり、戦争の正当性の有無は問われず、戦争そのものの規制は放棄され、全ての戦争が合法とされたのです。
ただ、かろうじて、戦時状態のもとでの行為を規律する国際法規則(戦時国際法)が形成されるにとどまりました。
つまり戦争の「やり方」だけが問題にされていたのです。
一方で、意外なことですが、ヨーロッパ列強国どうしの戦争は、1870~71年のプロイセン・フランス戦争以来、長らく絶えていました。その間に兵器の近代化も着々と進んでいたのですが、その意味するところが明らかになったのは、「第一次世界大戦」(1914~18年)のことでした。この戦争は、当初の予想に反して「国家の総力戦」の様相を呈するようになり、戦車・戦闘機・潜水艦などの近代兵器が次々と登場し、その死者は民間人を含めて2000万人に達したと言われています。
また、この戦争は、ロシア革命(1917年)発生の直接の契機ともなりました。国民に多大な犠牲を強いる戦争を続ければ革命が起きる…という現実は、各国の指導者に強い危機感を与えたのです。
かくして、第一次世界大戦後、初めて、「戦争違法化」への動きが生まれました。
その1つが、1928年に締結された「戦争放棄に関する条約」です。これは、
- 「締約国は国際紛争解決の為戦争に訴ふることを非とし且其の相互関係に於て国家の政策の手段としての戦争を放棄することを其の各自の人民の名に於いて厳粛に宣言す」
- 「締約国は相互間に起こることあるべき一切の紛争又は紛議は其の性質又は起因の如何を問わず平和的手段に依るの外之が処理又は解決を求めざることを約す」
という内容でしたが、わが国をはじめ15カ国が調印して成立し、後に約60カ国が参加しました。
この条約は、一見してわかるとおり、我が憲法の9条1項の原型となったものです。この条約により、歴史上初めて、「侵略戦争が違法である」ことが確認されました。
ただ、この条約には重大な欠陥がありました。それは、参加国の多くが「自衛」のために戦争に訴える権利を留保し、また、違反行為に対する罰則が定められていなかったことです。
しかも、世界大恐慌(1929年)は、同条約締結までの国際協調の雰囲気を一変させました。貧困の中からファシズムが台頭してゆき、世界は、第二次世界大戦(1939~45年)に向かって突き進んでゆくことになります。わが国も、泥沼の日中戦争に突入し、やがて大戦争の中心的な当事者となって、国土は焦土と化しました。
第二次世界大戦の人的・物的な被害は、先の大戦とは比べものにならない大規模なものでした。死者数だけでも5000万人を越えたという統計があります。しかも、この大戦において、究極の近代兵器=「核兵器」が広島と長崎で使用されました。何とかしなければ「戦争による人類の破滅」が現実のものになることが誰の目にも明らかになっていたのです。かくして、1945年には「国連憲章」が制定され、「国際連合」が創設されました。
国連憲章は「国際の平和及び安全を維持すること」を第一の目的とし、
- 「すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない」(2条3項)
- 「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない外のいかなる方法によるものも慎まなければならない」(同4項)
と規定しました。
これは従前の戦争違法化の流れをより一層推し進めるものでした。また、国連憲章が提言した平和のための「集団的措置」(「集団的安全保障」構想)は、いわば「世界警察」を創設するという画期的な構想でした。これと、新たに創設された「国際司法裁判所」とが相まって、「戦争放棄に関する条約」の抱えていた弱点の克服が試みられました。
つまり、「国際紛争」は話し合いとルールで解決しなければならない。それに違反した国は処罰される…これが、国連憲章の構想です。
これは、個人の間と同じことです。個人の間の争いも、たとえどんな理由があろうとも、暴力を使って解決してはいけません。それは犯罪として処罰の対象となります。そういうアタリマエのことが、国家間のルールとして確認されたのです。
また、「戦争」の問題を「憲法」で取り上げることも一般的になってきました。
今や、150を越える国が、憲法の中に何らかの「平和主義条項」を設けているといいます。
つまり、民主主義・福祉国家とならび、平和の実現こそ、20世紀の世界が目指したものだったのです。
このことを、「絵本」では
- 「いろいろな国があれば、争いごとも起きる」
- 「ここはどこの土地?」
- 「この石油はどこの国がつかう?」
- 「ケンカが起きるのは、人間と一緒」
- 「でも」
- 「ケンカをしてもなぐってはいけない」
- 「人をころしてはいけない」
- 「だから」
- 「戦争もいけない」
- 「争いごとは、話し合いとルールで解決する」
- 「それが、『人間の智恵』」
と表現しました。
さて、9条1項の文言をお読み頂ければおわかりのように、これは、「戦争放棄に関する条約」を叩き台にして、「戦争」のみならず「武力による威嚇又は武力の行使」も、「国際紛争を解決する手段」(=「国益」を守る手段)としては、「永久にこれを放棄する」としたものです。
「武力による威嚇又は武力の行使」の放棄は国連憲章でも規定されていることですから、9条1項とは、国際法で確認されている常識的内容を簡潔に確認したものといってよいでしょう。
ところが、イラク戦争以降、「国益」のために戦争に参加すべきかどうかが堂々と議論されているのには驚きます。
後にも触れますが、アメリカ・イギリスが強行したイラク戦争は、国際法に違反する侵略戦争でした。しかし、アメリカが起こした戦争に協力しなければ同国との関係を損ね「国益」に反するのではないか…そういうことが新聞や雑誌などで堂々と論じられていたことは記憶に新しいところだと思います。
しかし、「国益」のために戦争をすることは許されない。それは「戦争放棄に関する条約」以来の国際常識です。その原点を忘れた議論が堂々となされているところに、現在の憲法論議の危うさが表れていると思います。
よその国で戦争はしない
9条2項 「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」
先ほど、9条1項は国際法の常識をまとめたものだと言いました。これに対して、日本の憲法の独自性が現れているのが9条2項です。ここで、憲法は「戦力不保持」と「交戦権否認」を宣言しているのですが、これほど徹底した規定は、いわゆる先進国の憲法では類を見ません
ただし、このような徹底した規定を設けなければならなかった経緯は、それほど胸を張れるものではありません。それは、日本が、「戦争放棄に関する条約」に違反した国だったからです。
日本は、1928年に同条約の締約国となりながら、世界大恐慌を契機にして、中国への侵略戦争を始めます。すなわち、1931年には「満州事変」を起こし、37年には「盧溝橋事件」をきっかけに「シナ事変」へと突入していきました。
現在では「日中戦争」と呼ばれる戦争を、あえて「事変」と呼んだのは、「『戦争』ではないから『戦争放棄に関する条約』には違反していない」と強弁するためです。しかし、そんな理屈は通らず、アメリカなどから経済封鎖をされると、「自衛」のために、太平洋戦争へと突入してゆきました。
つまり、「戦争放棄に関する条約」では戦争を防げなかった。それが日本の特殊性なのです。9条1項のほかに2項が加えられたのは、1項だけでは国際世論の納得が得られない…「もう2度と戦争はしません」と言っても信用してもらえなかったからなのです
しかし、9条2項の内容は、世界史的に見て、先駆的なものと評価できます。
なぜなら、軍隊を持っていれば、それを使いたくなるのが世の常だからです。どうせ使ってはいけない「戦力」なら、最初から持たない方がいい。しかも、どの国も日本の憲法にならえば、世界から戦争はなくなるわけですから、極めて合理的な発想といってよいでしょう。
ただ、憲法制定当時は、先ほども紹介した国連主体の「世界警察」構想が実現すると考えられていました。万一、他国からの侵略を受けても、いつかは「世界警察」が助けてくれる…そういう前提があったのです。しかし、米ソ冷戦は、国連憲章の理想を現実化することを阻んでしまいました。集団的安全保障構想の中核となるべき「安全保障理事会」は常任理事国の拒否権でマヒしてしまい、世界警察にあたる正式な「国連軍」は1度も組織されることはありませんでした。
しかも、1949年に中国で毛沢東率いる社会主義政権が誕生し、50年には朝鮮戦争が勃発します。日本は、アメリカから「反共の防波堤」と位置づけられるようになり、51年には「日米安保条約」が締結されました。それと平行して、50年には「警察予備隊」が、54年には「自衛隊」が発足します。
ご存じのとおり、この「自衛隊」と9条2項の関係は、約半世紀にわたり、わが国の憲法論争の中心にありました。
「自衛隊が違憲なのか合憲なのか」という問題については、弁護士会の中でも見解が分かれており、軽々に結論を出すことは出来ません。
ただ、少なくとも歴代の政府見解では、「自衛隊」は、合憲であり続けてきました。その事実は無視できません。政府の理屈を簡単に説明すると、「他国から侵略を受けた時に、国民の安全を守ることができなければ国家としての義務を果たしたことにならない。従って、他国から武力攻撃があった場合に、それを排除するために必要最小限度の範囲で実力を行使することは、自己防衛そのもので当然認められる。
また、そのための必要最小限度の実力、つまり自衛隊を保持することも禁じられていない」というものです。
この政府見解は現在も維持されており、国民も、そのような見解を持つ政党が政権につくことを50年以上の長きにわたり支持してきたのです。
さて、ここでポイントとなるのは、政府見解にあっても、「軍隊」と「自衛隊」とは違うとされていることです。
では、どこが違うのでしょうか?
たとえ「軍隊」であっても、侵略戦争ができるはずはありません。国連憲章上合法とされている戦争しかできないからです。では、「合法な戦争」にはどんなものがあるのでしょうか。それには3つの類型がああります。1つは「個別的自衛権」の行使としての戦争です。2つ目は「集団的自衛権」の行使としての戦争です。3つ目は、国連の「集団的安全保障活動」として行われる場合…つまり安全保障理事会の「武力行使容認決議」がある場合です。「軍隊」であれば、この3つの類型のどれかにあてはまれば、合法的に戦争をすることができるわけです
これに対し、「自衛隊」では、1.「他国からわが国に対する武力攻撃があること」が実力行使の条件になります。2.また、「必要最小限度の範囲での実力行使」ですから、他国からの武力攻撃を排除する…つまりわが国の領土から追い出す以上のことはできません。追撃の手は国境線でストップさせなければならない。たとえ敵国であっても、他国で戦闘行為をしてはならないのです。それゆえ、「自衛隊」は、「軍隊」であれば参加できる「集団的自衛権」の行使としての戦争にも、国連安全保障理事会の武力行使容認決議がある戦争にも参加することはできません。なぜなら、いずれも、わが国に対する武力攻撃がないのに、他国で戦闘行為をする場合にあたるからです。
では、個別的自衛権の行使はどうでしょうか。実は、政府解釈を前提にすると、自衛隊は本来の意味での個別的自衛権をも行使することはできません。なぜなら、国際法上、他国から武力攻撃(侵略)を受けたときには、反撃の延長として、敵国で戦闘行為をすることが認められているからです。
しかし、自衛隊はそれができない。それが「交戦権否認」の意味なのだとされています。このように考えると、政府解釈を前提にしても、9条2項は、侵略戦争を防止するという意味では、一つの明確かつ有効な基準であると言えましょう。海外で戦闘行為をしないで他国を侵略することなど、論理的に不可能だからです。
以上のことを、「絵本」では
- 「でも、戦争はなくならない」
- 「人間はよわい」
- 「武器を持っていると使いたくなる」
- 「戦争をしたくなる」
- 「だから、武器を持たないのも一つの智恵」
- 「でも、ほかの国から攻められたらどうする?」
- 「これは…難しい」
- 「でも、攻められてもいないのに戦争をするのはやめよう」
- 「日本の外で戦争をするのはやめよう」
- 「日本の憲法は、リーダーが勝手に戦争をすることを禁止した」
- 「それが、『日本の智恵』」
と表現しました。
とはいえ、9条2項は現在でも憲法改正論議の中心にあり続けています。その「廃止」ないし「改正」を求める意見は、極めて根強いし、弁護士会内にも様々な意見があります。決して、「9条2項堅持」でまとまっている訳ではありません。
しかし、9条2項をめぐる議論は、必要以上に混乱しているように思えます。それを整理した上できちんとした議論をすることは可能です。以下、幾つかの意見について検討してみましょう。
まず、「自衛隊の存在を認めるために、9条2項を改正すべきだ」という意見があります。確かに、「自衛隊が合憲か違憲か?」という論争は、現在も決着はついていません。それに決着をつけるために憲法を変えようというわけです。
しかし、50年以上も政府解釈で合憲であるとされていたものの存在を認めるために、なぜ、今、明文改憲の必要があるのか?…今ひとつ説得力を欠くように思います。また、湾岸戦争以来現在まで議論されているのは、自衛隊の「海外での戦闘行為」を認めるかどうかです。それが認められれば、もはや、それは「自衛隊」ではなく「軍隊」です。その意味でも、この意見はピントがずれていると言わねばなりません。
次に、「自衛隊は、実態としては軍隊そのものなのだから、それにあわせて9条2項を変えるべきだ」という意見があります。確かに、「最小限度の実力」と言いつつ、日本の「軍事費」(正確には「防衛費」)は世界屈指で、装備の内容もハイレベルなものとなっています。しかし、自国に対する武力攻撃がなければ戦闘行為ができない、他国での戦闘行為はできない…という法的縛りがかかっている以上、それはあくまで「軍隊」ではなく、「自衛隊」なのです。
そのことを証明したのが「イラク戦争」でした。様々な議論がありつつも、自衛隊の活動が「後方支援」にとどまったのは、それが「軍隊」ではなかったからです。後述のようにイラク戦争は違法な戦争でしたが、もし、日本の部隊が「軍隊」であれば、今頃、日本もこの泥沼の戦争に当事者として加わっていたことでしょう。「自衛隊は軍隊だ」という意見は、このことを無視した乱暴な議論であると言わねばなりません。
このように考えると、結局、問題は、「国連憲章」と「9条2項」とのズレを解消すべきかどうかに尽きます。特に、集団的自衛権の行使としての戦争、あるいは国連の集団的安全保障活動として行われる戦闘行為に参加すべきかどうかが問題となるでしょう。この点については、弁護士会の中にもいろいろな意見があります。しかし、議論の前提として、以下の点だけは、はっきりさせておくべきだと思います。
まず第1に、9条2項を削除すれば、わが国の憲法は「平和主義憲法」ではなくなります。前述のように、9条1項は国際法の常識をまとめたものに過ぎません。それをことさら「平和主義」と強調するのは、自ら「国際法音痴」であることを自白するようなものでしょう。
第2に、わが国には「ニセモノの集団的自衛権」論がまかり通っていることに注意しなければなりません。すなわち、マスコミを含め、「イラク戦争に参戦できなかったのは、集団的自衛権の行使が認められないからだ」という議論がなされていますが、これは大きな間違いです。なぜなら、国連憲章51条は集団的自衛権行使の要件として「武力攻撃」が発生したことを明確に要求しているからです。イラク戦争前、イラクはそのような武力攻撃をしていませんでした。
従って、この戦争が集団的自衛権の行使として正当化される余地はないし、アメリカやイギリス自身も、そんなことは言っていなかったのです。それなのに、日本では、これが「集団的自衛権」の問題として議論されている…これは深刻な勘違いだと言わねばなりません。アメリカが要求していたのは、国連憲章に挑戦するかのような「先制攻撃戦略」への協力です。それに協力することは、集団的自衛権の行使ではなく、国際法に違反する「集団的先制攻撃」となるのだということに留意する必要があります。
第3に、本来の意味での「集団的自衛権」も、冷戦の遺物に過ぎないということです。そもそも、国連憲章ができるまでは「集団的自衛権」という概念そのものがありませんでした。また、国連憲章の案にも「集団的自衛権」などという言葉は盛り込まれていませんでした。それは、当時から既に顕在化しつつあった米ソ対立を背景にして、アメリカが強引に主張して盛り込ませたものなのです。アメリカは、ソ連との対決をふまえ、かつ拒否権によって安全保障理事会の集団的安全保障体制が機能しないことを見越して、国連の枠組みを離れ「合法的」に軍事行動を取るためにこの規定を盛り込ませたという指摘もあります。従って、その歴史的沿革は改めて詳細に検討されるべきでしょう。冷戦が終結した今、むしろ問われるべきは、「集団的自衛権」がなお必要なのかどうかである可能性があるからです。
第4に、現在の国連の集団的安全保障活動は、国連憲章の規定とあまりにかけ離れていることです。本来の集団的安全保障活動のイメージは、「世界警察」を創設するというものです。だから、その活動全般について国連が責任を負う。しかし、今の安全保障理事会の活動は、個々の国の軍事行動に「お墨付き」の決議を与えることだけです。この違いは大きいと言わねばなりません。そして、その違いの持つ意味が顕在化したのもイラク戦争でした。実は、アメリカが、今回のイラク戦争の大義名分としたのは、国連安保理決議です。具体的には1991年の安保理決議687号と、2002年11月の1441号です。前者は、湾岸戦争の終結にあたり、和平の条件としてイラクが大量破壊兵器を破棄すること、武器査察を無条件で受け入れることなどを定めたものです。後者は、イラクが前者で定められた義務を履行していないことを遺憾としたうえで、このまま義務違反が続けばイラクは「重大な結果に直面するであろう」と警告するものでした。
とはいえ、これはアメリカやイギリスの一方的な軍事行動を認めるものではありません。それなのに、アメリカとイギリスは、ありもしない決議を「ある」と強弁して戦争を強行したのです。そんなことができたのも、安保理の活動が単なる「お墨付き」を与える活動にとどまっているからだと言わねばなりません。
第5に、それとも関連しますが、現在の国連の集団的安全保障活動には、事後チェックの仕組みがありません。安全保障理事会は「拒否権」を持つ大国の行為を裁くことができません。しかも、アメリカをはじめ、多くの国が「国際司法裁判所」や「国際刑事裁判所」の裁判を受けることを拒否しているのです。
第6に、「海外で戦闘行為をしない国」だからこそできる「国際貢献活動」も沢山あるということです。現に、戦地アフガニスタンにおいてすら、多数の日本人が、軍閥の武装解除や現地住民の生活支援のための活動に携わっています。それは、現地の人々の「戦争をしない国から来たスタッフ」への信頼感あってこそだと言われています。
また、一国で対応できない世界的課題が山積みになっている現在、軍事と関係のない「国際貢献」の方法はいくらでもあるはずです。そちらの可能性を検討せぬまま「軍事」ばかり強調するのであれば、「国際貢献」といいつつ、実は「国益」の確保が主たる目的ではないかと疑われても仕方がないでしょう。
戦争は最大の人権侵害
前文 「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」
先ほど、日本の平和主義憲法の独自性は9条2項にあると言いました。
ただ、理念的に言うと、より特徴的なのは、いわゆる「平和的生存権」を規定した前文の記述です。「平和」の問題を「人権」の問題として捉える…これは「戦争」というものの本質を考える上で、極めて重要な視点を提供してくれます。
一般に「戦争」が語られるとき、「愛する人や家族を守るために戦い、死ぬ」と美化されることが多いようです。しかし、それは正確ではありません。戦争とは「国を守るため」(侵略戦争であれば「国益」を守るため)に行われるものです。
従って、ひとたび戦争が起きれば、「国家が勝つために個人が死ぬ」か、「個人が生きるために国家が滅びる」かという、究極の選択が迫られることになります。このようなむきだしの対立が起きれば「国家緊急権」などといって、「法の支配」など吹き飛んでしまいます。全ての価値が「国家が勝つこと」に集約されてしまう。かつての日本のように「国体護持のため、最後の1人まで闘って死ぬべし」という結論となるのは自明のことでしょう。まして、戦争の相手となる国の人の命などどうでもよくなってしまいます。
つまり、「戦争」こそは最大の人権侵害であり、立憲主義の最大の敵なのです。先ほど紹介したように、国際法によって侵略戦争が違法とされるとともに、平和主義が立憲主義の原則として承認されていったのは当然のことと言えましょう。そして、その本質は、「国家権力に対する戦争の禁止」なのです。
このことを、「絵本」では、
- 「戦争をしたら人が死ぬ」
- 「人が人をころす」
- 「みんなで作った国なのに」
- 「その国が人をころす」
- 「『お国のため』に、ころす」
- 「…何で?」
と表現しました。
ところが、公にされた明文改憲案の大半が、前文の「平和的生存権」の規定を削除しています。もし、それが「戦争は人権侵害である」との認識を否定する趣旨なのだとすれば、極めて問題です。
また、その中には「平和主義」と「国際協調主義」を同義のものとするものがあります。しかし、それでは「平和主義」の本質が「国家権力に対する戦争の禁止」であることが曖昧にされてしまうでしょう。
「変えにくい」から憲法
96条1項 「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」
先ほど、憲法は最高権力者である「国民の代表者」を縛るためにある「最高法規」だと言いました。
裏返せば、「憲法」とは、権力者にとって一番邪魔なものです。だから、権力者が、それを自分に都合のよいように変えたいと思うのはむしろ当然です。それを防ぐため、どこの国の憲法でも、これを改正する手続は厳重になっています。
それは、簡単に変えられるような憲法は、「最高法規」としての役割を果たすことができないからです。
そして、わが憲法も、96条で、憲法を改正するについては、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で発議した案について、さらに国民投票で過半数の賛成を得る事が必要とされています。
このことを、「絵本」では
- 「憲法はリーダーを縛るもの」
- 「リーダーにとって一番じゃまなもの」
- 「だから、簡単には変えられない」
と表現しました。
ところが、公にされている明文改憲案の大半が、96条1項を改正して、もっと変えやすい憲法にしようと提案しています。その多くは、「時代の変化に機敏に対応できるようにすべきだ」というのですが、「変えにくい」ところに憲法の本領があるということが軽視されているのではないかと危惧されてなりません。
また、その中身を見ると、当初は「憲法改正国民投票を廃止して、国会だけで改正できるようにしよう」というような極端なものがありました。最近でも、国会の発議要件を「各議院の総議員の三分の二」から「過半数」に緩和するといった意見が有力に主張されています。そして、それに対する受け止めも、「その程度ならば大したことはない」というものが多いようです。
しかし、「3分の2」でなく「過半数」でよいとなると、改正の発議は、十分な議論もないまま、頻繁になされてくることでしょう。なぜなら、わが国では「議院内閣制」が取られ、さらに選挙制度として「小選挙区比例代表制」が採用されているからです。もともと内閣が衆議院の過半数の議員によって支持されている上に、少数政党が排除され、しかも党議拘束が強力です。両議院の過半数の同意を取ることはそれほど困難なことではありません。
ちなみに、「時代の変化への対応」ということの中身として、「名誉権」や「プライバシー権」あるいは「知る権利」といった「新しい人権」を憲法に明記する必要がある…と主張するものがあります。しかし、これらの権利については、既に、最高裁判所が、13条や21条の解釈を通じて、基本的人権として保障されることを確認しています。
なるほど、これらの権利を憲法の明文に反映させることに弊害があるとは思えませんが、今まで国会がそのための改正を発議してこなかったのは、その必要性がなかったことの裏返しでもあります。これを口実にして、「憲法を変えやすく」することは、かえって、基本的人権の保障を危うくすることに注意する必要があるでしょう。
君たちが大人になるころ
12条 「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」
97条 「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」
もともとこの「絵本」は、中学生を対象として企画されたものです。
憲法改正国民投票の手続を定める法律が制定された今、彼ら彼女らが大人になるころ、主権者としての判断を迫られることになるかも知れない…
その思いを、「絵本」では
- 「君たちが大人になるころ」
- 「憲法が変わるかもしれない」
- 「変えるか、変えないか」
- 「それは、君たちが決める」
と表現しました。
ただ、そこに込めた思いは、単に若い人たちの票がどう動くかといったレベルの話だけではありません。
97条は「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」だと言いますが、それを裏返せば、憲法とは現実に起きた「失敗の集大成」なのです。
人類が、なぜ、失敗を繰り返してきたかというと、憲法は「守らなければならない」ルールではあるけれども、「守るのが大変」なルールでもあるからです。
例えば、これからも憲法を守って行くためには、「21世紀型貧困」をどうやって解決するのかという難問に立ち向かわなければなりません。また、「戦争」についても、「平和主義」を貫徹しようとすれば、戦後日本の後ろ盾となってきたアメリカとの関係をどうイメージしてゆくのか?…という難問に突き当たります。
これらは、まさに、若い人たちに課された課題です。憲法を守り続けることができるかどうかは、「不断の努力」(12条)によって、これらの諸問題を解決することができるかどうかによって決まる。その期待を込めて、
- 「変えるか、変えないか」
- 「それは、君たちが決める」
と書いたのです。
ただ、一方で、これは若い人たちにとって、「生き甲斐」を得る場が無数にあることをも意味しています。世界的に見ても、「環境破壊」と「貧困」と「戦争」の悪循環が人類を滅ぼすのではないかと危惧されていますが、それを回避する課題と、憲法を守る課題とは、多くの部分で重なります。理系・文系を問わず、若い人たちにとって、「なすべきこと」は沢山あるのです。
是非、皆さんには、立派な「個人」となって、その自主性で「国」を支える人材となっていただきたい。そして、それぞれの価値観に従って「なすべきこと」と「生き甲斐」を見つけ、自分の人生の主人公となっていただきたい…そのメッセージをもって、この「解説」を締めくくらせていただきます。
【 おわりに 】
「絵本」とうってかわり、この「解説」では、かなり専門的なところにまで突っ込んだ議論を紹介させていただきました。
これは、今の憲法改正論が、学校で教えられている一般的な憲法理解のあやふやなところを突いて出てきているからです。そこをきっちりと議論をしようとした分、いささか難解なものとなってしまったかも知れません。
この点については、今後、いろいろな工夫をしてゆかなければならないと思っています。
他方、ある程度憲法の勉強をされてきた方々にとって、この「絵本」及び「解説」の視点は、相当に新鮮なものであったのではないかと思います。
憲法改正が現実の政治課題になったことを危惧する声もありますが、それ以上に、「憲法は当然正しい」という前提を捨て、原点に立ち帰った議論がなされるようになったことは、わが国の憲法文化を大きく前進させています。現に、この十数年で、憲法学の内容はすっかり様変わりしました。憲法の基本理念に立ち帰り、法哲学や政治学の力も取り入れて、憲法のあり方を追求するダイナミックな議論の成果は目を見張るものがあります。
私達は、この「絵本」及び「解説」を作成するにあたり、できるだけ、その成果を取り入れるべく努力しました。なぜなら、それらは、主権者たる皆さんが、将来、一票を投じるにあたり、大変参考になる内容だと思ったからです。
とはいえ、「学問」の世界の議論ですから「正解」はありません。また、正直、実務家に過ぎぬ私達が、学者の皆様の議論を正確に理解し、整理しきれているかどうかについては、皆様の批評を待つ必要があるでしょう。これらの点については、様々な意見をいただきつつ、必要に応じて修正してゆきたいと考えています。
ただ、いずれにせよ、憲法改正に向けた国民的議論の「たたき台」としては、それなりの水準のものが仕上がったと自負しています。この出版が、憲法を真に国民のものとするための一助になるのであれば、望外の幸せです。
 奈良弁護士会
奈良弁護士会